「ジョーカー・ゲーム」と「VIVANT」の面白さ
2023年の夏、日本のエンターテイメント界は一編のテレビドラマによって席巻された。TBS日曜劇場『VIVANT』。堺雅人演じる主人公・乃木憂助が所属する、政府非公認の自衛隊秘密情報部隊「別班」の存在は、視聴者に強烈なインパクトを与え、瞬く間に社会現象となった。その壮大なスケールと謎が謎を呼ぶ展開は、これまで日本のドラマでは稀有であった「スパイ・諜報」というジャンルへの関心を一気に再燃させたのである。
この熱狂の渦中で、多くの視聴者や書評家の間で、ある種のデジャヴ(既視感)が囁かれ始めた。「この設定、どこかで見たことがある」。その声が指し示した先こそ、柳広司による傑作スパイミステリー小説『ジョーカー・ゲーム』シリーズであった。『VIVANT』の主人公を想起させるというレビューが散見されるように、第二次世界大戦前夜の日本を舞台に、帝国陸軍内に設立された架空のスパイ養成機関「D機関」の暗躍を描いたこの作品は、『VIVANT』の登場によって再び脚光を浴びることとなった。
本稿の目的は、この二つの作品、すなわち『VIVANT』に登場する「別班」と、『ジョーカー・ゲーム』の「D機関」を比較考察することにある。特に、両組織の根幹をなすスパイの「訓練内容」に見られる驚くべき類似点を分析の起点としたい。なぜ、時代も設定も異なる二つの物語で、これほどまでに似通ったスパイ養成のメソッドが描かれるのか。その共通点と、そこから浮かび上がる思想的な相違点を徹底的に解き明かすことで、それぞれの作品が持つ独自の魅力、とりわけ『ジョーカー・ゲーム』が内包する奥深い独創性を掘り下げていく。最終的には、日本のエンターテイメントにおけるスパイ物語の系譜を辿り、我々がなぜ「見えない存在」の戦いにこれほどまでに惹きつけられるのか、その本質に迫ることを目指す。
「死ぬな、殺すな」vs「国を守る」D機関と別班、その訓練と哲学
『ジョーカー・ゲーム』のD機関と『VIVANT』の別班。両組織は、その存在自体が国家の「影」であり、所属する諜報員は超人的な能力を持つエリートとして描かれる。その根幹をなすのが、彼らを常人から「スパイ」へと変貌させる特殊な訓練である。このセクションでは、両組織の訓練内容とその根底に流れる哲学を徹底的に比較・分析し、その類似性と決定的な差異を明らかにする。
酷似する超人的な訓練内容 — 観察眼と記憶力の極限テスト
両作品のファンが最も強く類似性を感じるのは、諜報員に求められる基礎能力、特に「観察力」と「記憶力」を試す訓練であろう。これらは単なる能力テストではなく、極度のプレッシャー下で冷静さを保ち、膨大な情報を瞬時に取捨選択・整理する、スパイとしての思考様式そのものを涵養するための試金石である。
『VIVANT』において、別班に入るための登竜門とされるのが、陸上自衛隊小平学校(現・情報学校)の「心理戦防護課程」である。この課程の入校試験について、ジャーナリスト石井暁氏の著作『自衛隊の闇組織 秘密情報部隊「別班」の正体』では、元隊員の証言として、以下のような異様な質問が紹介されている。
「先ほどの休憩時間にトイレに行ったな。そのトイレのタイルの色を言え」
「今入ってきた男の眼鏡のフレームは何色だったか」「右手には何を持っていたか」
(出典:kusanomido.com)
これらの質問は、被験者が意識的に注意を払っていないであろう日常の風景の細部を問い、無意識下での情報収集能力と記憶の定着度を測るものだ。風景を単なる「景色」としてではなく、常に情報の集合体として捉える訓練の入り口と言える。
一方、『ジョーカー・ゲーム』では、こうした訓練風景が直接的に描かれることは少ない。しかし、D機関員たちはその成果を任務遂行の中で遺憾なく発揮する。例えば、第一話「ジョーカー・ゲーム」で、監視役として派遣された佐久間中尉がD機関員たちとポーカーに興じる場面。機関員たちはカードの配られ方、互いの表情や些細な癖から、佐久間が陸軍の密命を帯びていることまで見抜いてしまう。これは、単なるゲームの腕前ではなく、卓上の全ての情報を統合し、相手の心理状態や背景までを瞬時に分析する、まさにD機関の訓練の賜物である。彼らにとってポーカーは、諜報活動の縮図であり、観察力と心理戦の実践演習なのである。
さらに、尾行、追跡、変装、潜入、開錠、暗号解読といった実践的なスパイ技術も、両組織に共通する必須科目だ。別班の訓練では、朝鮮総聯幹部への食い込みや地方都市の権力構造調査といった、極めて実践的かつ危険な内容が含まれるとされ、D機関員たちもまた、世界各地で見知らぬ土地に溶け込み、”見えない存在”として活動する。これらの技術は、スパイが自らの身を守り、任務を完遂するための鎧であり武器に他ならない。訓練内容の酷似は、諜報活動という特殊な任務が、時代や組織の別なく普遍的なスキルセットを要求することの証左と言えるだろう。
D機関「死ぬな、殺すな」と別班「国益のための超法規的措置」
しかし、これら酷似した訓練の先に目指す「理念」において、D機関と別班は決定的な対立を見せる。訓練が「How(いかにして)」を教えるものならば、理念は「Why(なぜ)」に答えるものだ。この「Why」の違いこそが、両作品の物語の質を根本的に規定している。
D機関の創設者である結城中佐が掲げる理念は、あまりにも有名である。
「死ぬな、殺すな、とらわれるな」
(出典:ピクシブ百科事典)
この三原則は、当時の帝国陸軍が掲げる「生きて虜囚の辱めを受けず」という精神主義や、「お国のために命を捧げる」という自己犠牲の美学とは完全に真逆のベクトルを向いている。結城にとって、スパイの死や殺人は、情報を持ち帰るという本来の目的を達成できない「最悪の選択肢」であり、単なる任務失敗を意味する。そこには愛国心や忠誠心といった情念が入り込む余地はなく、ただひたすらに目的達成のための合理性が貫かれている。D機関員は国家の駒である前に、自らのスキルを駆使してゲームをクリアする究極のプロフェッショナル、孤高の「ゲームプレイヤー」として描かれる。彼らの忠誠は、国家や軍ではなく、結城中佐が提示する「ゲームのルール」そのものに向けられているのだ。
対照的に、『VIVANT』で描かれる別班の行動原理は、熱い「使命感」と「愛国心」に根差している。彼らのスローガンは「美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない」(出典:東京新聞)。この言葉が示す通り、彼らの目的は、日本の国益を脅かす内外の敵を排除することにある。そのためには、殺人を含む超法規的活動も辞さない。乃木憂助がテロ組織「テント」と対峙する姿は、冷徹な情報収集活動というよりは、むしろ国家の「正義」を執行する「影の戦士」の様相を呈している。彼らの活動は、時に武力行使を伴い、D機関の非暴力的な諜報活動とは一線を画す。別班のメンバーは、自らの命を賭してでも国家に殉じる覚悟を持った、紛れもない「愛国者」なのである。
キーポイント:理念の比較
- D機関:徹底した合理主義。「死ぬな、殺すな」は、情報を持ち帰るという目的を最大化するための手段。スパイは国家の駒ではなく、究極のスキルを持つ「ゲームプレイヤー」。
- 別班:強い愛国心と使命感。「国益」のためなら超法規的措置も厭わない。スパイは国家を守るための「影の戦士」。
結論として、D機関と別班は、スパイに求められるスキルセットという点では驚くほど共通しているが、そのスキルを何のために使うのかという根本的な思想において、全く異なる組織として設計されている。この思想的対立こそが、両作品のキャラクター造形、物語構造、そして読者・視聴者が抱くカタルシスの種類を決定づけているのである。
柳広司が描く「ジョーカー・ゲーム」の独創性
『VIVANT』との比較を通じて、柳広司が創造した『ジョーカー・ゲーム』の世界がいかに独創的であるかが一層鮮明になる。それは単なるスパイ小説の枠を超え、キャラクター造形、物語構造、そして歴史解釈において、他の追随を許さない独自の美学を確立している。このセクションでは、『ジョーカー・ゲーム』ならではの魅力を多角的に分析する。
「顔のないスパイ」たちの美学と物語構造
『ジョーカー・ゲーム』の最も際立った特徴の一つは、その特異なキャラクター造形と、それを活かすための物語構造にある。
まず、原作が複数の短編で構成された「連作短編集」である点が極めて重要だ。各話で主役となるスパイが異なり、読者は特定の主人公に感情を固定することなく、次々と展開される鮮やかな「ゲーム」そのものに焦点を当てることになる。このオムニバス形式は、個々の諜報戦の緻密さや、どんでん返しがもたらす知的興奮を最大化する効果を持つ。読者の興味は「このキャラクターはどうなるのか」という感情移入から、「この難局をどう切り抜けるのか」という純粋なミステリー的興味へとシフトする。これは、主人公・乃木憂助の過去や家族の因縁が物語全体を強力に牽引する『VIVANT』の直線的な物語構造とは好対照をなしている。
この構造を支えるのが、「個性を排した」キャラクター造形だ。D機関員たちは本名を捨て、偽名を使い、過去の経歴を全て消去することで、自らを「見えない存在」とすることを徹底する。結城中佐は「十年、二十年……あるいはもっと長く、見知らぬ土地にたった一人で留まり、その地に溶け込み、”見えない存在”とならなければならない」と語る。この哲学は、2016年に放送されたテレビアニメ版の演出にも色濃く反映された。アニメ版では、主要なD機関員たちのキャラクターデザインが意図的に似せて描かれており、「誰が誰だか分かりにくい」という声が視聴者から上がったほどだ。しかし、これは原作の「スパイは目立たぬことを旨とする」という本質を忠実に映像化した、極めて意図的な演出であった。さらに、豪華声優陣は感情を抑えた抑制的な演技に徹し、キャラクターの「個」を消すことで、逆に彼らのプロフェッショナル性と組織としての異様さを際立たせることに成功した。
この「顔のなさ」こそが、『ジョーカー・ゲーム』の美学の核心である。彼らは人間的な感情や個人的な背景を物語の推進力としない。女性さえも任務のために「利用するもの」として割り切り、必要とあらば家族すら捨てて次の任地へ向かう。そこにあるのは、感傷を排した冷徹な機能美だ。読者や視聴者は、彼らの内面に深く共感するのではなく、彼らが繰り広げる華麗な頭脳戦の「観客」として、その手際の見事さに感嘆する。この突き放した距離感が、作品にクールでスタイリッシュな独特の読後感を与えているのである。
歴史の「if」を紡ぐスパイ・ミステリー
『ジョーカー・ゲーム』のもう一つの独創性は、史実とフィクションを巧みに融合させ、歴史の「if」を読者に提示する点にある。
物語の舞台は、昭和12年(1937年)の日中戦争勃発から太平洋戦争に至るまでの、世界情勢が最も緊迫した時代である。柳広司は、日独防共協定や上海の国際都市(魔都)といった実在の事件や場所を背景に設定することで、物語に圧倒的なリアリティと説得力をもたらしている。例えば、日本陸軍の対ソ謀略や日独関係といった複雑な国際政治が、D機関員たちの諜報戦の背景でリアルに動いている。これにより、彼らの活動が単なる空想の産物ではなく、歴史の大きなうねりの中で行われているのだという緊張感が生まれる。
さらに重要なのは、D機関が帝国陸軍という巨大組織の中で「異端」の存在として描かれている点だ。当時の陸軍は、精神論や根性論が支配する世界であり、D機関の徹底した合理主義は全く相容れないものであった。作中では、陸軍精神を体現する風戸中佐率いる「風機関」が、D機関を潰すために同じ任務で競わされるエピソードが描かれる。この対立構造は、単に物語にスリルを与えるだけでなく、D機関の存在そのものが、当時の日本の組織論や精神主義に対する痛烈な批評となっていることを示している。
D機関の活躍は、どれほど華々しくとも、歴史の大きな流れ、すなわち日本の敗戦という結末を変えることはできない。彼らがどれだけ優秀であっても、より巨大な組織の非合理性によってその成果は十全に活かされず、戦争突入という「敗北」を回避できないという皮肉が、物語全体を覆っている。ここに、柳広司の批評的な視点が光る。彼は、D機関という架空の組織を通じて、「もしも当時の日本に、これほど冷徹で合理的なインテリジェンス機関が存在していたなら、歴史は少しは違ったものになっていたのではないか」という、痛切な歴史の「if」を読者に問いかけているのである。それは、スパイアクションの興奮を超えた、知的な思索を促す、極めて文学的な試みと言えるだろう。
虚構と史実の交差点 — 陸軍中野学校の影
『ジョーカー・ゲーム』と『VIVANT』。この二つの物語が放つリアリティの源泉をたどると、一つの実在した組織に行き着く。それは、大日本帝国陸軍が秘密裏に運営したスパイ養成機関、「陸軍中野学校」である。この歴史上の存在が、虚構の物語に確かな輪郭と説得力を与えている。本セクションでは、この「影の学校」と両作品の関係性を解き明かす。
D機関と別班、共通のルーツ「陸軍中野学校」
陸軍中野学校は、1938年(昭和13年)に設立された、諜報、防諜、謀略、宣伝といった「秘密戦」の専門家を養成するための軍学校である。その存在は極秘とされ、卒業生は軍服を脱ぎ、一般人に紛れて国内外で特殊任務に従事した。彼らの教育内容は、語学や国際情勢の分析はもちろん、変装術、写真術、開錠術といった実技に至るまで多岐にわたったという。その教育方針は、画一的なものではなく、学生の自主性や創意工夫を重んじるものであったとされる。
この陸軍中野学校と両作品の関係性は、明確に区別して理解する必要がある。
まず、『ジョーカー・ゲーム』のD機関は、作者の柳広司が陸軍中野学校を「モデル」として創造した、完全なフィクション上の存在である。しかし、その設定の細部には中野学校の影が色濃く落ちている。例えば、陸軍内にありながら陸軍の主流から外れた異端の組織である点や、一般社会の知識を持つ人材を登用した点などは、史実の中野学校の側面を反映している。だが、最も重要なのは、柳広司がその「精神」を意図的に反転させたことだ。中野学校の根底には「功は語らず、語られず」「国と国民の捨て石となれ」という、国家への滅私奉公の精神があった。これに対し、結城中佐は「死ぬな」と真逆の理念を掲げる。これは、史実を単に模倣するのではなく、批評的に解釈し、全く新しいフィクションとして昇華させた、作者の創造性の証左である。
一方、『VIVANT』に登場する「別班」は、陸軍中野学校の史実の系譜を継ぐ存在として描かれている。これはフィクション内の設定ではあるが、現実の歴史的文脈と強く結びついている。戦後、陸軍中野学校の関係者の多くが、警察予備隊(後の自衛隊)の情報部門創設に関与したことは、複数の研究で指摘されている。特に、陸上自衛隊小平学校(現・情報学校)は中野学校の事実上の後継機関と見なされており、その「心理戦防護課程」は別班員の養成コースであると噂されてきた。『VIVANT』で示唆される訓練内容と、現実の小平学校や戦時中の中野学校の入校試験の類似性は、ジャーナリストによって驚きをもって報じられている。つまり、別班は「中野学校の亡霊」とも言うべき、歴史の連続性の上に成り立つ存在として物語にリアリティを与えているのだ。
このように、D機関と別班の訓練手法が酷似しているのは、両者が「陸軍中野学校」という共通のオリジンを持つからに他ならない。一方は史実を大胆に反転させたフィクションとして、もう一方は史実の延長線上にあるリアルな組織として。この虚実の交差点に立つことで、両作品は単なる空想譚ではない、歴史の重みを感じさせる物語としての強度を獲得しているのである。
なぜ私たちはスパイ物語に惹かれるのか
『ジョーカー・ゲーム』と『VIVANT』。二つの物語は、共に「陸軍中野学校」という史実の影を背負いながら、そのアプローチと目指す地平において全く異なる、しかし等しく魅力的なスパイ物語として成立している。本稿の考察を締めくくるにあたり、両作品が提示する魅力の本質を再確認し、現代においてスパイ物語が持つ普遍的な引力について考察したい。
まず、二つの物語が提供する「面白さ」の質は明確に異なる。
『ジョーカー・ゲーム』が提供するのは、極めてクールでスタイリッシュな「頭脳のゲーム」の面白さだ。そこでは、組織の論理や時代の狂気といった巨大な奔流に対し、D機関員たちが「個」の知性とスキルだけを武器に挑んでいく。彼らの戦いは感情的ではなく、チェスプレイヤーが盤面を読むように冷徹で計算高い。読者はその鮮やかな手際に感嘆し、複雑なプロットが解き明かされる瞬間に知的なカタルシスを得る。それは、混沌とした世界を明晰な論理で切り裂いていく爽快感に他ならない。
一方、『VIVANT』が提供するのは、スケールが大きくエモーショナルな「使命のドラマ」の面白さだ。主人公・乃木憂助は、国や家族という、より大きな物語のためにその身を投じる。彼の戦いは、個人的な過去の清算と、国家の安全保障という二つの重い使命を背負っている。視聴者は、彼の苦悩や葛藤に感情移入し、彼が困難を乗り越え、正義を執行する姿に心を揺さぶられる。それは、自己を超えた大義のために戦うヒーローの物語がもたらす、熱い感動である。
では、なぜ私たちは、アプローチは違えど、これらのスパイ物語に強く惹きつけられるのだろうか。それは、スパイという存在そのものが、現代社会を生きる我々の深層心理にある種の問いを投げかけるからではないだろうか。
姿を消し、名前を捨て、自らを「見えない存在」とするスパイは、アイデンティティが常に問われる現代において、究極の匿名性を体現する。彼らは、極限の状況下で、己の知力と精神力だけを頼りに、虚構と真実が入り乱れる世界を生き抜く。その姿は、正体不明の情報が飛び交い、何が真実か見えにくい現代社会のメタファーとも言える。私たちは、彼らが繰り広げる情報戦の中に、自らが日常で直面する複雑な状況を生き抜くためのヒントや、あるいは一種の代理満足を見出しているのかもしれない。
最終的に、『ジョーカー・ゲーム』も『VIVANT』も、国家と個人、正義と悪、忠誠と裏切り、虚構と真実といった、時代を超えた普遍的なテーマを扱っている。そして、私たちに「見えない世界」の扉を少しだけ開き、その向こう側で繰り広げられる人間たちの壮絶なドラマを垣間見せてくれる。その知的好奇心を刺激し、スリルへの欲求を満たしてくれる力こそが、私たちがスパイ物語に永遠に魅了され続ける理由なのである。

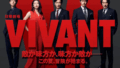

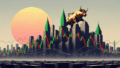
コメント