はじめに
マネーフォワード ME は銀行・証券・クレジットカード等の複数口座を一元管理できる家計簿アプリです(スマホ版、デスクトップ版)。 銀行口座や証券口座など様々な機関を一括登録すれば、収支状況や資産の推移を自動でグラフ化・分析してくれるため、資産が散在していても一目で状況が把握できます。 無料版でも主な機能(自動収支記録や基本の予算設定など)が使えますが、プレミアム版では過去1年以上のデータ閲覧や口座5件以上の連携が可能になります。 本レポートでは、年代別・家族構成別にマネーフォワード ME の活用方法を整理し、若年期から高齢期に至るまで、豊かなライフプランニングを実現するポイントを紹介します。
若年期(20代~30代前半):家計と資産形成の基礎を築く
収支と貯蓄の見える化: 独身時代や共働き期間といった若年期は、子どもがいないため大きな支出が少ない「お金のためどき」です。 収入がまだ多くないかもしれませんが、この時期に「お金を貯める習慣」を身につけることが将来に繋がります。 マネーフォワード ME を使えば、毎月の収支を自動で記録し、グラフやレポートで支出の内訳を把握できます。 クレジットカードや電子マネーの支出も連携すれば手入力が不要で、キャッシュレス時代の支出管理をラクにしてくれます。 特に便利なのは、収入と支出のタイミングがリアルタイムで把握できることです。 これにより、月末の残高不足に悩むことがなくなり、安心してお金を使い分けられます。
貯蓄の自動化と目標設定: 若年期には「先取り貯蓄」を徹底し、手取り収入の20%を貯蓄することが推奨されます。 給料日に自動で貯金に回す仕組み(勤務先の財形貯蓄や銀行の自動積立定期預金、自動積立投信など)を活用すれば、「余ったら貯金」ではなく「貯金から使う」という習慣を身につけやすくなります。 マネーフォワード ME では、この貯蓄口座も連携しておけば、貯めている金額や残高を常に把握できます。 また、「NISA」など少額から始められる資産形成制度を積極的に活用しましょう。 たとえばつみたてNISAでは、年間120万円までの投資利益が非課税になるため、複利効果を最大限に享受できます。 20代で始めた投資は将来の大きな資産につながるため、資産形成の第一歩としてNISAを使いこなすことが重要です。
支出の可視化と無駄の洗い出し: 収支が安定している時期なら、家計簿ではじめて見える化できた支出の内訳によって、「どこにお金を使っているか」を分析できます。 たとえば、外食費や交際費が多めになっているなら、オーダーを見直したり、お酒の代わりに安価な活動を取り入れたりするなど、具体的な節約策を立てやすくなります。 マネーフォワード ME は支出カテゴリの自動分類やグラフ表示も備えているため、自分の支出傾向を直感的に把握できます。 実際、「自分だけのオリジナル家計簿を作ることで、削るべき支出と大切なお金の使い方が見えてくる」という声もあります。 無駄な支出を洗い出し、逆に自分にとって大切なこと(旅行やスキルアップなど)にお金を割くように優先順位を付けることで、可視化→改善→循環という好循環が生まれます。 家計簿をつけること自体が蓄財につながることも多く、「家計簿をつけてみたら驚くほどお金が貯まるようになった」というユーザーの声もあります。
家計簿の続け方: 若いうちは忙しい中でも家計簿をつけ続けるのは難しいかもしれません。しかしマネーフォワード ME は手間がかからず、使いやすさと分析のしやすさからかんたんに家計を見直せるので、継続しやすいアプリです。 特に銀行やカードを連携して自動で記録してくれる機能が魅力で、比較したアプリの半数以上は自動連携が無かったとのことですが、マネーフォワード ME は購入履歴から支出を自動記録できるため手入力の負担がほぼゼロです。 さらにレシート読み取り機能を使えば現金支出も手軽に記録できます。 1ヶ月間のプレミアム版は無料体験できるため、機能を試しながら自分に合ったプランを見つけられるのも利点です。 無料で十分な人も多いですが、金融機関を10件以上連携したい場合や、過去データの詳細分析が必要な場合はプレミアムにするとよいでしょう。 プレミアムでは口座5件以上の連携や一括更新が可能になり、常に最新の家計簿を維持できます。 無料版でも「家計簿をつけているだけでお金が貯まる」効果は期待できますが、プレミアム版の機能を活用すればより的確なライフプランニングが可能になります。
オススメの活用ポイント: 若年期のマネーフォワード ME 活用ポイントをまとめると以下の通りです。
- 自動収支記録: 銀行・カードを連携して収支を自動記録し、手間を省く。
- 先取り貯蓄: 手取り収入の20%を貯蓄に回す(財形貯蓄や自動積立などで実現)。
- NISA活用: 少額から始められるNISAを積極的に活用し、複利効果を享受する。
- 支出の分析と改善: 支出カテゴリのグラフ表示で無駄を洗い出し、節約と大切な支出のバランスを図る。
- プレミアムの活用: 無料で試し、プレミアム版で必要な機能(口座5件以上の連携や過去データ閲覧など)を使いこなす。
以上により、若年期に家計管理の基礎を築き、貯蓄・投資の習慣を身につけることができます。これらの習慣は将来の大きなライフイベントでも活かせる財産となります。
壮年期(30代後半~40代):安定収入時代の家計管理とライフプランニング
結婚・子育て・住宅購入という大きな支出: 30代後半から40代にかけては、結婚、出産、住宅購入、子育てなど人生で最もお金がかかる「お金のかかりどき」に突入します。 住宅購入資金や教育資金といった大きな支出が連続して発生するため、夫婦で協力し計画的にお金を管理することが不可欠です。 マネーフォワード ME は夫婦で家計簿を共有する機能もあります。 具体的には、共同の生活費口座や貯蓄口座、家計用クレジットカードなど、ふたりに必要な金融機関だけを選んで共有できます。 お小遣い口座など個人的なものは共有しないようにすることでプライバシーも保護されます。 共有した口座情報を基に収支を自動で家計簿に反映し、支出の傾向を円グラフで確認できるため、夫婦で家計の見える化を行い協調することが容易になります。 マネーフォワード ME は2025年9月に新機能「シェアボード」を提供開始しており、プレミアム会員同士で夫婦・家族と一緒に日々の家計や資産状況を確認できるようになりました。 この機能により、夫婦で共同の家計簿をチェックし合うことで、家計改善や資産管理が捗ります。 節約して浮いたお金で夫婦の時間をもっと楽しむ――そんな未来を目指せるよう、まずはお金の共有と見える化を進めましょう。
住宅ローンと債務管理: 住宅購入時には大きな負債(住宅ローン)を抱えることになります。 住宅ローンは人生で最大の借入額であり、無理のない借入額を設定することが何より重要です。 一般的には年収の5~7倍程度が無理のない目安とされています。 マネーフォワード ME では住宅ローンの残高を管理する機能もあります。 手入力で残高や返済額を登録することで、「まだ○○万円残っている」「○年後に返済完了」といった計画を立てやすくなります。 また、住宅ローンの残高を視覚化することで、「家の価値はどれくらいあるか」「残債はいくらか」を把握できます。 マネーフォワード ME では住宅ローン残高をグラフ表示し、残債が減っていく様子を確認できます。 たとえば「住宅ローンを借りられることと無理なく返済できることは違う」ことを常に意識し、返済余力があるかをチェックしておくことが重要です。 住宅ローンの返済期間は年齢に影響されますが、70歳以上になって返済が終わるケースもあるため、適切な返済計画を立てる必要があります。 マネーフォワード ME を使えば、住宅ローン残高と住宅の価値を比較したり、返済余力を計算したりすることも可能です。 これにより、債務超過にならない住宅価格の管理や、必要に応じて住宅ローンの見直し(減額・固定利率化など)も検討しやすくなります。
教育費・保険の見直し: 子どもが増えると教育費が膨大な支出になります。 大学費用は数百万円単位にもなるため、計画的な貯蓄が不可欠です。 例えば、児童手当を全額貯蓄すれば大学入学までに約200万円を準備できるという計算もあります。 マネーフォワード ME では教育費に充てる貯金口座を設定し、残高や月額の貯蓄額を把握できます。 また、子どもが生まれたことで必要な保障が変わります。 死亡保障や医療保障が家族構成に合っているか、無駄な保険料を払っていないか、定期的に見直しましょう。 特に住宅ローンを組む際には団体信用生命保険が入る場合がありますので、そのタイミングで死亡保障の見直しを行うとよいでしょう。 マネーフォワード ME では保険料の支出を家計簿に記録できるため、保険料の内訳を確認して無駄がないかチェックできます。 また、年金や公的年金の残高も把握しておくと安心です。マネーフォワード ME では年金口座を登録すれば、現在の年金残高や将来の支給予測を確認できます。 高齢期に向けて、公的年金だけでは老後の生活が不安にならないか、資産の一部を投資信託や定期預金に振り向けて準備するなど、多層的な老後資金準備を行いましょう。
資産形成の深化: 壮年期は収入が安定しているため、資産形成をより積極的に進める好機です。 マネーフォワード ME のプレミアム版には、「資産形成アドバンスコース」というサービスがあります。 これはリーズナブルな「スタンダードコース」に加え、より積極的な資産形成を目指す方に向けたコースで、配当情報の自動見える化や資産配分のグラフ表示など高度な機能が提供されます。 例えば配当履歴や予測、内訳をグラフ化して表示してくれるため、株式投資の成果を常に把握できます。 また、業種別や自己定義のカテゴリで資産配分を確認できるため、資産のバランスをチェックしやすくなります。 比較的リスクを取れる20~30代なら、資産配分を確認しながらより株式の配分が多いポートフォリオに変更するなどの対策を取れます。 一方、40代以降は資産形成と老後資金準備のバランスを取る必要があります。 この時期には「お金のかかりどき」が訪れるため、ライフプランニングを行いましょう。 何歳で子どもが生まれ、何歳で家を買い、教育費がいくらかかるかなど、ライフイベント別にお金の計画を立てることで、漠然とした不安が具体的な計画へと変わります。 マネーフォワード ME では、将来の目標資金を設定して見える化する機能もあります。 例えば「○○万円の教育費を○年で貯めたい」「定年までに○年分の生活費を貯めたい」といった目標を入力すると、月々の貯蓄額や残高推移がシミュレーションされます。 これにより、目標に向けた積極的な貯蓄・投資計画を立てやすくなります。 また、夫婦で共同でライフプランを作ることで、将来の夢や不安についてオープンに話し合い、夫婦で協力して実現できるようになります。 必要に応じて、ファイナンシャルプランナーに相談することも有効です。 マネーフォワード社では、ユーザーがお金の相談をしたい場合にオンラインで無料で相談可能なサービスも提供しています。 納得できるまで何度でも相談でき、本当に最後まで無料で利用できます。 壮年期にはこのようにプロとの協力も視野に入れつつ、マネーフォワード ME を使って資産形成とライフプランニングを両立させましょう。
オススメの活用ポイント: 壮年期のマネーフォワード ME 活用ポイントをまとめると以下の通りです。
- 夫婦での家計共有: 生活費口座や貯蓄口座を共有し、夫婦で家計簿をチェックし合う。
- 住宅ローン管理: 残高や返済計画を手入力登録し、債務超過にならないよう管理する。
- 教育費準備: 教育費貯金口座を設定し、子どもの教育費を計画的に貯蓄する。
- 保険・年金の見直し: 家族構成に合わせて保険を見直し、必要な保障を確保する。
- 資産形成アドバンスコース: プレミアムの資産形成コースを活用し、配当や資産配分を把握しながら投資を最適化する。
- ライフプランニング: 将来の目標(教育費、住宅ローン返済、老後資金など)を設定し、月々の貯蓄・投資計画を立てる。
- 専門家との相談: 無料でFPに相談できるサービスを利用し、ライフプランの検証やアドバイスを得る。
以上により、壮年期には安定収入を活かして資産形成を加速しつつ、大きな支出に備えた計画的な家計管理を行います。夫婦で協力し、ライフプランを共有することで、将来の不安を減らし、より豊かな人生を歩むための鍵となります。
中年期(50代):老後資金の準備と家計再編の時期
老後資金の確保とインフレ対策: 50代になると、子どもが成人して独立したり、住宅ローンの返済が終わったりすることもあります。しかし一方で、老後の生活費準備が急務になります。日本では年金のみでは老後の生活が不安になりがちです。そこで、50代であっても投資を始めてお金の目減りを防ぐ必要があるでしょう。 マネーフォワード ME のプレミアム版では、資産配分をグラフ表示しているため、自分の資産のバランスを確認しやすくなります。 例えば、株式や不動産、現金などの内訳を把握できれば、将来のインフレに備えて株式比率を調整したり、安定収入源の確保を図ったりできます。 また、配当収入を増やすことも老後の安定につながります。マネーフォワード ME の資産形成アドバンスコースでは、配当履歴や予測をグラフ化してくれるため、株式投資の配当収入を見える化できます。 50代になっても投資に遅すぎることはありません。特に現在は賃金や物価が上がり始めており、インフレ傾向が続けばお金の目減りを防ぐためにも、50代から積極的に投資を始めることが大切です。 マネーフォワード ME は、保険や不動産なども含め投資を通じた資産形成に役立つサービスを紹介してくれるため、自身の状況に合った投資プランを考える参考にできます。 さらに、老後資金の一部を年金や公的年金と合わせて管理することも検討しましょう。マネーフォワード ME では年金口座を登録すれば、現在の年金残高や将来の支給予測を確認できます。 「公的年金だけでは不安だ」と感じるなら、資産の一部を定期預金や投資信託に振り向けて老後資金を多層化しましょう。
家計の再編と節約: 50代になると家族構成も変わり、夫婦で二人暮らしに戻ったり、子どもが離れて一人暮らしになったりすることもあります。この時期には家計の再編が必要になることがあります。たとえば、住宅ローンの返済が終わったら家賃や固定費が減りますし、子どもがいなくなったら食費や教育費が減るでしょう。しかし同時に、保険料の支払いや医療費など新たな支出が発生したり、夫婦での二人暮らしに適した支出構造に見直す必要があるかもしれません。 マネーフォワード ME では、固定費と変動費を整理しておくことで、ただの記録から改善に活かせる家計簿へとステップアップできます。 具体的には、光熱費や保険料は一度見直してしまえば月々の支出をおさえやすいため、定期的に見直しましょう。 特に保険の加入はライフステージに合わせて変わりますので、50代で不要な保障を減らし、医療や介護などに備えるように調整します。 また、スマホ契約の見直しや光熱費のキャンペーン利用など、小さな節約でも積み重ねれば大きな効果があります。 たとえば、大手キャリアから格安スマホへ乗り換えると夫婦2人で月に1万円程度削減できる場合もあります。 電気や都市ガスも地域によって安い会社があるため、比較して安いところへ乗り換えるのも良いでしょう。 これらの節約策を実践し、月1万円程度の節約を継続すれば25年間で300万円以上の差が出てきます。 少しずつの積み重ねが老後の生活に大きく影響するため、50代でも節約の継続が重要です。マネーフォワード ME では支出のグラフやレポートを活用して、節約の効果をチェックしやすくなります。 節約して浮いたお金は投資や貯金に回すことで、資産形成にも繋げられます。
副業や収入アップの検討: 50代でも働き続ける場合が多いですが、転職や副業で収入を増やす検討も有効です。 もし転職で収入が減る可能性があれば、副業OKの勤務先を選んだり、配偶者が副業やアルバイトで働くなど、収入アップの余地を探りましょう。 例えば、配偶者が厚生年金に加入して収入を上げれば、世帯全体の収入を増やすことができます。 実際、配偶者が半分の保険料負担で厚生年金に加入すれば、自身の老後年金も増やせるメリットがあります。 マネーフォワード ME では、夫婦の収入を合わせて管理できるため、副業収入や配偶者の収入も含め総合的な収支を把握できます。 また、50代で起業するケースもあります。マネーフォワード社は50代起業のアイデア20選など、起業に関するサービスも提供しています。 起業の準備や資金調達には家計の状況をしっかり把握する必要があるため、マネーフォワード ME で資産と負債をチェックし、無理のない範囲で挑戦することが重要です。 副業や起業で得られた収入は、老後資金の増強や家族との未来のために役立てましょう。
生活設計と健康管理: 50代になると仕事や家庭での責任感が増す一方、自分の健康や親の介護問題なども家計や健康に影響します。 この時期には、単に家計を管理するだけでなく自分と家族の生活設計を考えることも大切です。マネーフォワード ME では、将来の目標資金を設定する機能を活用し、「○年後に旅行をしたい」「○年後に扶養控除を終えても生活が不安なくなるよう○万円の資産を用意したい」といった目標を立てることができます。 目標を設定すれば、それに向けた月々の貯蓄・投資計画が立てやすくなります。 また、ファイナンシャルプランナーとの相談もこの時期には有効です。マネーフォワード社では無料で相談できるため、ライフプランの詳細な検証や将来の不安(介護費や病気対策)についてプロのアドバイスを得ることができます。 さらに、50代以降は健康管理も家計に影響します。高齢になると医療費が増えることもありますので、保険の見直しや医療費の見える化を行いましょう。 マネーフォワード ME では医療費をカテゴリに分類できるため、毎年の医療費の推移をチェックし、保険加入状況や医療費の節約策を検討できます。 また、健康に投資することも長期的な家計に良い影響を与えます。 ジム会費や健康食品など、自分の健康に投資する支出も見える化し、適切な範囲で行っているか確認しましょう。 生活設計と家計管理を両立させることで、50代以降も豊かで安心した生活を送れるようになります。
オススメの活用ポイント: 中年期(50代)のマネーフォワード ME 活用ポイントをまとめると以下の通りです。
- 老後資金の積極的な準備: 資産配分を確認しつつ、株式や投資信託で老後資金を積み増しする。
- 配当収入の活用: 配当履歴を見える化し、安定収入源を増やす。
- 家計の再編と節約: 固定費の見直し(光熱費・保険料の見直しなど)と小節からの節約を行う。
- 収入アップの検討: 副業や配偶者の収入増強などで収入を増やし、老後資金を厚くする。
- 生活設計と目標設定: 将来の目標(旅行や健康管理、扶養控除終了後の生活設計など)を設定し、それに向けた貯蓄・投資計画を立てる。
- 専門家との相談: 無料でFPに相談し、ライフプランや介護費対策などを検証する。
以上により、中年期には老後資金の確保と家計の再編を行い、自分と家族の未来を守り抜きます。50代は資産形成と老後資金準備のバランスを取る時期ですが、マネーフォワード ME を活用すれば、計画的に老後の生活設計を進めることができます。
高齢期(60代~):資産維持と生活設計の時期
老後資金の管理とライフプランの実現: 60代になると退職し、老後の生活に移行します。この時期には、若年期・壮年期に積み上げた資産を老後の生活費や医療費に活かしていきます。マネーフォワード ME では、資産の残高と内訳を常に把握できるため、老後の資金をどう運用するか計画を立てやすくなります。 たとえば、定年後の月々の生活費がいくら必要か、現在の資産でいくらまで維持できるかをシミュレーションします。 マネーフォワード ME では、将来の目標資金を設定してシミュレーションできるため、「定年後に○年分の生活費を貯めたい」という目標を立てれば、それに必要な月額の貯蓄額や残高推移が表示されます。 資産を活用していく際には、資産運用のバランスを考えることが重要です。定年後は現金性の資産(定期預金や年金)と株式・不動産などの資産を適切に配分し、安定収入と価値維持を両立させます。 マネーフォワード ME では、プレミアム版の資産形成コースで資産配分のグラフを確認できるため、自分のポートフォリオが適切かチェックできます。 また、配当収入を活かして老後の生活費を賄うことも検討しましょう。マネーフォワード ME では配当収入を見える化してくれるため、株式投資や投資信託の配当収入がどれくらいあるか把握できます。 配当収入が安定していれば、それを老後の生活費に充当することで、資産を減らさず生活を維持できます。 もちろん、投資には元本割れのリスクもあるため、配当収入だけではなく残高の減りすぎに注意します。 マネーフォワード ME では、資産の推移をグラフ化しているため、「資産が減っている」「どこの資産が減っているか」を把握できます。 老後資金を維持・増やすためのバランス運用を心がけましょう。
健康管理と医療費の見える化: 高齢期になると医療費や介護費が大きな支出になることがあります。そこで、マネーフォワード ME では医療費を分類して管理し、毎年の医療費の推移を確認できます。 例えば、病院費用、薬代、介護費などをそれぞれカテゴリに記録すれば、どの分野で支出が増えているかがわかります。 医療費の見える化により、必要な医療には十分備えつつ、無駄な支出を減らすことができます。 また、保険の見直しも高齢期には重要です。加入している保険が全て必要か、見直して不要なものは削減しましょう。 特に老後の医療費をカバーする公的年金や厚生年金はもちろん、必要に応じて長期介護保険の見直しや医療保険の補助保険(メディゴール)の加入も検討します。 マネーフォワード ME では保険料の支出を家計簿に記録できるため、保険料の内訳を確認して無駄がないかチェックできます。 健康管理にもお金をかけることは、結果的に医療費を減らすことにつながります。 高齢になっても運動や食事管理を続けることで、病気を防ぎ医療費を節約できます。 マネーフォワード ME では健康に関する支出(ジム会費や健康食品など)も記録できるため、適切な範囲で投資しているか確認できます。 また、介護費についても見える化すると安心です。介護保険の見直しや、将来的に介護を必要とする場合の費用を見積もっておくことで、家計に計画的に備えられます。 マネーフォワード ME では、将来の目標資金を設定して「○年後に介護費○万円を準備したい」といった計画も立てられます。 健康管理と医療費の見える化により、高齢期でも安心して生活できるようになります。
ライフプランの実現と資産移転: 60代以降は、若年期に描いたライフプランの実現時期です。たとえば「○○歳で旅行をしたい」「○○歳で子供や孫にお金をあげたい」といった目標を、この時期に実現できます。マネーフォワード ME では、そうした具体的な目標を設定しておけば、それまでの貯蓄・投資がどれだけ達成につながっているかを確認できます。 達成していない場合でも、残りの年数を活かして補填する計画を立てることができます。 また、高齢期には資産の移転も考える必要があります。子どもに資産を引き継ぐ場合、相続税の見直しや信託の活用などを行うことで、子どもに多く残せるようにします。マネーフォワード ME では資産の残高や構成を把握できるため、相続税対策を講じるためのデータとしても役立ちます。 もちろん、ライフプランは柔軟に変更できます。健康や経済状況によっては、目標を後回しにしたり、逆に前倒しにしたりすることもあります。マネーフォワード ME では、目標資金の計画を随時更新できるため、状況に応じて柔軟にライフプランを調整できます。 例えば、病気で予想以上に医療費がかかった場合には旅行の計画を後回しにし、医療費準備に回す、といった具合です。 ライフプランは変化しても良いのですが、マネーフォワード ME で見える化しておくことで、自分や家族が安心して目標を追求できるようになります。
生活設計と幸せ: 高齢期には「お金」だけでなく「人生の充実」も大切です。マネーフォワード ME を使ってお金の面倒を見ることで、人生の他の面にも時間を割けるようになります。 家計が見える化され、ピンとこない不安が減れば、自分たちの好きなことに時間を充てられるようになります。 たとえば、孫と遊ぶ時間や趣味を楽しむ時間、旅行や学びを通じた人生の充実を図る時間などです。 マネーフォワード ME では、節約して浮いたお金で夫婦の時間をもっと楽しむ――そんな未来を目指せるよう、まずはお金の共有と見える化を進めましょう。 マネーフォワード社のキャッチコピーにもあるように、「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というビジョンがあります。 お金を管理することは人生を豊かにする手段であり、高齢期になってもその重要性は変わりません。マネーフォワード ME を活用して、自分の資産状況を常に把握しつつ、自分のライフプランを実現していきましょう。
オススメの活用ポイント: 高齢期(60代~)のマネーフォワード ME 活用ポイントをまとめると以下の通りです。
- 老後資金のバランス運用: 現金性資産と株式・不動産を適切に配分し、安定収入と資産維持を両立させる。
- 配当収入の活用: 配当収入を見える化し、それを老後の生活費に充当する。
- 医療費の見える化: 医療費を分類して管理し、毎年の推移を確認して不要な支出を減らす。
- 保険・介護費の見直し: 必要な保障を確保しつつ、不要な保険料を削減する。
- ライフプランの実現: 具体的な目標(旅行、趣味、相続など)を設定し、それに向けた資産運用を行う。
- 相続税対策: 資産の残高を把握し、相続税見直しや信託の活用などで子どもに多く残せるようにする。
- 人生の充実: 家計を管理することで時間を稼ぎ、自分たちの好きなこと(孫との時間、趣味、学びなど)に充実して過ごす。
以上により、高齢期には資産を維持しつつ生活設計を実現し、幸せな老後を送れるようになります。マネーフォワード ME を使ってお金の面倒を見ることで、人生の他の面にも時間を割けるようになり、より豊かで安心した暮らしが可能になります。
夫婦・家族での家計共有と資産管理
マネーフォワード ME は、夫婦や家族でお金を共同管理するための機能も備えています。特に壮年期や高齢期になると、夫婦で家計を一緒にするケースが増えます。 ここでは、夫婦・家族での家計共有の方法とポイントを紹介します。
シェアボードによる共同管理: マネーフォワード ME の新機能「シェアボード」を使えば、夫婦や家族でお金を共有管理できます。 シェアボードは、ホスト(招待する側)とゲスト(招待を受ける側)で構成され、プレミアム会員同士、もしくはプレミアム会員と無料会員のペアで利用できます。 まずホスト側でゲスト(例:配偶者)を招待し、ゲスト側で招待を承認することで、共有するアカウントを選択できます。 ポイントは、共有する金融機関を自由に選べることです。 生活費や貯蓄に使う口座だけを選んで共有し、お小遣い口座などは自分だけで閲覧するようにすることで、プライバシーを守りつつ家計を共有できます。 共有した口座情報を基に、2人のお金の収支や資産状況が自動でまとめられるため、夫婦で同じ家計簿をチェックできます。 例えば、生活費口座の残高や支出内訳が双方で共有されるため、夫婦で共同の予算を立てやすくなります。 また、共有した金融機関の情報を合算して一つの家計簿や資産状況が自動作成されるため、夫婦で同じデータを見ることができます。 これにより、「この月は○○が多めだ」「この支出を減らそう」といった協議がスムーズに行えます。 実際、シェアボード導入後は「夫婦で共同の家計簿をチェックし合うことで、家計改善や資産管理が捗ります」という声もあります。 節約して浮いたお金で夫婦の時間をもっと楽しみましょう――そんな未来を目指せるよう、まずはお金の共有と見える化を進めましょう。
共有できる機能とプライバシー: シェアボードでは、家計簿や資産状況の自動作成、支出の自動分類、グラフやレポートの共有など、基本的な家計管理機能が双方で利用できます。 例えば、夫婦で共同の生活費口座の残高を確認したり、支出カテゴリ別のグラフを見たりすることができます。 また、シェアボードには共有された口座のみが表示されるため、お小遣い口座など個人的なものは見えません。 共有する口座を選ぶ際には、「共通の生活費口座や貯蓄口座、家計用クレジットカードなど、2人に必要な金融機関だけを選んで共有」するようにしましょう。 「お小遣い口座のように共有したくないものは変わらず自分のアカウントだけで閲覧」できます。 これにより、夫婦間でプライバシーを尊重しつつ共同でお金を管理できます。 シェアボードは現在プレミアム会員向け機能ですが、2025年時点で利用者は1730万人を超えており、今回の新機能で個人に加えて「ふたり」のお金もまとめて管理できるようになると報じられています。 夫婦で家計を共有するメリットは、協調性が増して家計が安定することです。 「2人で同じ家計簿をチェックできるので、家計改善・資産管理が捗ります。節約して浮いたお金で2人の時間をもっと楽しみましょう!」というマネーフォワード社のコメントもあるように、お金の話でも夫婦で意見を合わせることで夫婦関係の強化にもつながります。
家族全員での管理: シェアボードは夫婦だけでなく、親子や兄弟姉妹など家族全員でも共有できます。 例えば、家族で一つの家計簿を共有し、生活費や貯金を共同で管理することも可能です。 特に子どもがいる家庭では、子どもが学生の時期に家族で共同貯金口座を使い、教育費や将来の出費を計画的に貯めることも考えられます。 シェアボードで家族全員が家計の状況を見える化できれば、家族で協力して貯金や節約を行うことができます。 ただし、子どもが未成年の場合、親が主導して共有する形になるでしょう。また、兄弟姉妹で資産を共有する場合(例:親の遺産を均等に分けて管理する等)にも、シェアボードは有用です。 共有する口座や情報を調整しつつ、家族でお金の共有を進めることで、家族全体の経済的な安定と信頼関係の強化につながります。
夫婦・家族での家計共有コツ: 最後に、夫婦や家族で家計を共有する際のコツをいくつか紹介します。
- お互いに誠実に: 家計の共有はお互いに誠実で開かれた関係が大切です。小さな支出でも共有し、悩みや意見を話し合いましょう。
- 目標を共有する: 夫婦でライフプランを共有し、目標(例:老後の旅行や子どもの教育費)を共に意識することで、協力しやすくなります。
- 役割分担: 家計管理における役割を協議し、誰がどの口座を管理するか決めておくとスムーズです。例えば「銀行口座の更新は夫が、カード支出は妻がチェックする」など。
- 定期的にレビュー: 月次や半年次に家計の状況をレビューし、目標に向かっているかチェックしましょう。マネーフォワード ME ではグラフやレポートがあるので、それを使って話し合います。
- プライバシーと尊重: お小遣いや個人の収入などは共有しないよう配慮し、プライバシーを尊重してください。 また、意見が合わない場合も冷静に話し合い、決められないことは協力会社(例:FP)に相談すると良いでしょう。
以上のように、マネーフォワード ME を活用すれば、夫婦や家族でお金を共有して管理することが容易になります。 お金の話は家族全員で協力することで、より安定した未来を築けるでしょう。
おわりに
マネーフォワード ME は、若年期から高齢期まで幅広いライフステージで活用できる家計簿・資産管理アプリです。 各年代・家族構成に応じて、その使い方を工夫することで、お金の見える化と計画的な資産形成を実現できます。若年期には貯蓄・投資の基礎を築き、壮年期には大きな支出に備えたライフプランニングを行い、中年期には老後資金の準備と家計再編を進め、高齢期には資産維持と生活設計を実現――このように時代ごとに異なる課題に向き合いつつ、マネーフォワード ME を使いこなすことで、人生の各段階で豊かなライフプランを歩んでいけます。 また、夫婦や家族でお金を共有管理することで、協調性が増してお金の不安も減ります。 無料で使える基本機能から、プレミアム版の高度な機能まで、マネーフォワード ME はユーザーのニーズに応える柔軟なツールです。 今後もマネーフォワード社は新機能の追加やサービス改善を続けているため、ぜひ最新情報も確認しつつ、自身のライフステージに合った使い方を模索してみてください。 お金を前に、人生をもっと前に――マネーフォワード ME を通じて、豊かで安心した未来を築いていきましょう。

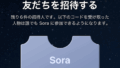

コメント