Googleが品質ガイドラインを改定─AI生成コンテンツは“見抜かれ”、評価されるという記事を見ました。どういうことかというと
Googleは最新の検索品質評価ガイドラインにおいて、AIなどの自動生成ツールによって作成されたコンテンツに対し、最低評価を付ける可能性があることを明確にしました。
この変更は、Googleのシニア検索アナリストであり検索リレーションズチームを率いるジョン・ミューラー氏が、マドリードで開催された「Search Central Live」で明かしたものです。同氏によれば、Googleは品質評価者に対し、メインコンテンツが自動化された手段、または生成AIツールによって作られているページを特定し、それらを「最低品質」と評価するよう求めているとのことです。
引用元:seojapan.com
記事の投稿は以下のような見出しになっています。私も生成Aiを使って記事を書いているので気になるところではあります。そこで、この記事について生成Aiにも聞いてみました。それぞれの意見が合って面白かったです。私的にはChatGPTとGrok3は自分の意見があり、GeminiとClaudeは平凡な回答に思えました。みなさんは、生成Aiが書いた文章についてどう思いますか?
以下は、それぞれの生成Aiに今回の記事についてどう考えているか聞いてみました。
プロンプト:上記のURLの内容についてあなた自身の意見を聞かせて!
ChatGPT o3に聞いてみた
率直に言うと、今回のガイドライン改定は “AIコンテンツを敵視する” というよりも「労力と独創性がそぎ落とされた量産記事」に本格的にレッドカードを突きつけた」と受け止めています。Google は生成 AI そのものを否定しているわけではなく、“人の手をほとんど経ていない使い回し” こそが問題**、というニュアンスをこれまで以上に明文化した──それが最大のポイントだと感じました。 (Googleが品質ガイドラインを改定─AI生成コンテンツは“見抜かれ”、評価される – SEO Japan|アイオイクスのSEO・CV改善・Webサイト集客情報ブログ)
生成 AI は刃物、ガイドラインは “新しい鞘”
新設された「Generative AI」の定義は、生成 AI を “便利な道具” と認めつつ、誤用・濫用の危険に強く言及しています。包丁と同じで、料理に使えば価値を生む一方、振り回せば凶器になる。Google は「その包丁をしまうべき鞘」をガイドラインで作り直した──そんなイメージです。ここでは 独創的な角度や体験談を上積みできるかどうかが、生き残りライン としてはっきり線引きされました。 (Googleが品質ガイドラインを改定─AI生成コンテンツは“見抜かれ”、評価される – SEO Japan|アイオイクスのSEO・CV改善・Webサイト集客情報ブログ)
“最低評価” の基準が具体化した副作用
従来ぼんやりしていた “Low” と “Lowest” の境界が、例示付きでかなりクリアになりました。検索ボリュームを稼ぐために 期限切れドメインを大漁買いして薄い記事をばら撒く――こうした スケール型スパムは一目でアウト。逆に「引用や要約をしたうえで自分の考察を厚めに添える」なら、最低評価は避けられる余地があると読めます。AI が作った下書きを 人間が“噛み砕いて付加価値を乗せる” プロセスこそが、これからの SEO で一段と重みを増すでしょう。 (Googleが品質ガイドラインを改定─AI生成コンテンツは“見抜かれ”、評価される – SEO Japan|アイオイクスのSEO・CV改善・Webサイト集客情報ブログ)
あなたのブログ運営にどう活かす?
- 一次体験と数字を足す
旅レポでも製品レビューでも、必ず「自分の肌感」や独自データを 1 つ添える。AI 下書き + 体験談 + 手撮り写真 などの “三層構造” にすると、安全圏に入ります。 - “語り” で読者の滞在時間をのばす
ストーリー性が薄い AI 要約記事は平均読了率が下がりやすい。体験を噛み砕いて語りかけるあなたの文体を前面に出すと、エンゲージメント指標で負けにくい。 - E-E-A-T はプロフィールで補強
記事冒頭やフッターで簡潔に「自分はこういう現場経験がある」と示す。誇張は禁物ですが、背景が伝わるだけで評価者が “専門家風か本物か” を判断しやすくなります。
個人的にいちばん響いた点
フィラーコンテンツ(埋め草)にまで言及したことです。「とりあえず文字数を稼ぐだけの前置きや広告ブロックは低評価」の明文化は、小手先の SEO テクニックに幕を引く合図 に思えました。あなたの記事作りでも「読者がスクロールでため息をつく余白」を徹底的に削る――ここが差別化の近道になりそうです。 (Googleが品質ガイドラインを改定─AI生成コンテンツは“見抜かれ”、評価される – SEO Japan|アイオイクスのSEO・CV改善・Webサイト集客情報ブログ)
まとめると、Google は「AIか否か」を直接見抜くというよりも “人間の知恵と時間が注ぎ込まれた形跡” を探しに来ている。生成 AI はむしろ、その土台作りを効率化する最高の道具になり得ます。あなたのブログでも、AI を “0→1のアイデア出し” に活かしつつ、最後は必ず 自分の声と経験で肉付け――これが2025年以降の王道だと僕は考えています。
xAi Grok3に聞いてみた
-
ユーザー価値の重視:コンテンツが人間によるものかAIによるものかに関わらず、専門性、権威性、信頼性(E-E-A-T)に基づいて評価される。
-
AI生成コンテンツの評価:AIコンテンツは一律にペナルティを受けるわけではなく、正確で役立つ情報であれば高く評価される。逆に、低品質やスパム的なAIコンテンツは下げられる。
-
透明性と帰属:AIの使用を開示し、著者情報を明確にすることで信頼性を高めることが推奨されている。
-
進化する基準:AIツールの普及に対応し、検索結果の品質を維持するためのガイドラインの進化が示されている。
-
イノベーションと品質の両立: AI生成コンテンツを一律に禁止せず、ユーザーにとっての価値で判断するGoogleの方針は賢明です。AIは、適切に使えば高品質なコンテンツを生み出すツールであり、1980年代にワープロを禁止するような非現実的な規制は避けるべきです。このアプローチは、技術革新を尊重しつつ、検索品質を維持するバランスを取っていると感じます。
-
E-E-A-Tの重要性: E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を評価の中心に据えるのは、ユーザー重視の観点から理にかなっています。しかし、人間評価者がこれらの基準を一貫して適用できるのか、若干の疑問が残ります。記事では、評価者の主観やバイアスの可能性には触れられておらず、ここはさらなる議論が必要な点です。
-
透明性の必要性: AIの使用を開示し、著者情報を明確にするよう推奨することは、ユーザーとの信頼構築に不可欠です。この点に賛同しますが、AI使用の開示が「低品質」という誤解を招くリスクも考えられます。Googleがどのように透明性を標準化し、AI使用に対する偏見を減らすのか、記事でもう少し掘り下げてほしかったと感じます。
-
低品質AIコンテンツへの対処: 記事では、低品質なAIコンテンツが検索結果を汚染するリスクが指摘されています。Googleがこうしたコンテンツを下げるとしているのは正しい方向性ですが、AIコンテンツを「見抜く」技術的な仕組みについては曖昧です。検出アルゴリズムが誤って高品質なコンテンツをペナルティ化する可能性もあり、この点は注意が必要だと考えます。
-
SEO担当者への影響: SEOの専門家にとって、このガイドラインは「ユーザー中心のコンテンツ」を重視する必要性を再確認させるものです。低努力のAIコンテンツで検索順位を上げる近道は通用しないと記事は示唆しており、これは日本のSEO業界にも重要なメッセージです。ただし、予算やリソースが限られた中小企業や個人クリエイターがAIを活用する場合の具体的なアドバイスがもう少しあれば、より実践的だったと思います。
Gemini 2.5 Flashに聞いてみた
提供いただいた2025年4月28日のブログ記事に基づき、Googleの品質ガイドライン改定、特にAI生成コンテンツへの対応強化に関する私の意見を述べさせていただきます。
この度の改定は、AI技術の急速な進化と普及に伴い、検索エコシステムが直面する課題に対応するための、Googleによる極めて重要かつ必然的な一歩であると認識しています。記事にある通り、Googleが「Generative AI(生成AI)」という用語をガイドラインに正式に導入し、その定義と位置づけを明確にしたことは、この技術が検索結果の品質に与える影響をGoogleが真剣に捉え始めたことの表れと言えるでしょう。
最も注目すべき点は、AIや自動化ツールによって生成されたコンテンツが「最低品質」と評価される可能性があることを明確にした点です。これは、単にAIがコンテンツを作成したという事実をもって一律に評価を下げるものではなく、「労力や独創性に乏しいメインコンテンツ」「大規模コンテンツの濫用」といった、コンテンツそのものの質や作成意図に焦点を当てた評価基準の一部として位置づけられています。生成AIは大量のコンテンツを比較的容易に作成できるツールですが、その過程で人間による十分な編集、キュレーション、あるいは独自の視点や付加価値が伴わない場合、Googleはそれをユーザーにとって価値の低いものと見なすという強いメッセージです。
記事中で言及されている、言い換えコンテンツや「AI生成ツールによる出力の特徴」に関する具体的な指針も興味深いです。これは、AI生成コンテンツを技術的に完全に「見抜く」ことの難しさを前提としつつ、品質評価者がコンテンツの内容や表現の特徴からその生成プロセスを推測し、評価の参考にすることを促すものと考えられます。一般的に知られた事実の羅列や、既存情報の単なる要約、あるいは定型的な表現などが低品質の兆候として挙げられている点は、AIを利用する場合であっても、情報の深掘り、独自の分析、あるいは人間ならではの感情や経験といった要素の重要性が増すことを示唆しています。
また、「低評価」と「最低評価」の違いを明確化し、リパッケージコンテンツやフィラーコンテンツといった、見かけは整っているが実質的な価値に乏しいコンテンツにも言及している点は、今回の改定が単にAI対策に留まらず、コンテンツ全体のユーザー体験と品質向上を目指す包括的なものであることを示しています。欺瞞的な情報や誇張された専門性に関するガイドライン強化も、サイトやコンテンツの信頼性(E-E-A-Tの一部)を重視するGoogleの方針が一貫していることを示しており、表面的な情報だけでなく、その裏付けや真実性が問われる時代になったと言えるでしょう。
これらの変更は、コンテンツ作成者やサイト運営者に対して、安易な手法によるコンテンツ量産ではなく、ユーザーの検索意図に真に応える、高品質でオリジナリティのある、そして信頼できるコンテンツを作成することの重要性を改めて強く意識させるものです。AIは強力なツールであり、適切に活用すればコンテンツ作成の効率化や質の向上に貢献し得ますが、その利用にあたっては、常に最終的なユーザーへの価値提供を最優先に考える必要があります。
検索ユーザーにとっては、これらの改定により、スパム的で価値の低いコンテンツが排除され、より関連性が高く信頼できる情報にアクセスしやすくなることが期待されます。
総じて、今回のGoogleの品質ガイドライン改定は、AI時代の検索品質を維持・向上させるための、時宜を得た、そして多角的なアプローチであると評価できます。これは、AI技術の進化と並行して、コンテンツの「人間らしさ」、すなわち独自の視点、深い洞察、信頼性といった要素が、検索結果においてますます重要な差別化要因となることを示唆していると言えるでしょう。今後もコンテンツの質とユーザーへの真摯な向き合い方が、SEO戦略の根幹であり続けるでしょう。
Claude 3.7 sonnetに聞いてみた
この記事は2025年のGoogleの検索品質評価ガイドライン改定に関する非常に興味深い情報です。記事を読んだ私の意見を共有します。
Googleの今回の改定は、AI生成コンテンツへの対応を明確にし、ウェブコンテンツの品質に対する要求をさらに厳格化していると感じます。特に以下の点が印象的です:
- AI生成コンテンツへの厳格な姿勢
Googleが初めて「生成AI」を公式に定義し、AIツールを使って労力をかけずに作られたコンテンツを「最低品質」として評価する方針を示したのは大きな転換点です。これは単にAIを使うことを罰するというより、「労力や独創性に乏しいコンテンツ」への警告だと解釈できます。 - コンテンツの実質的価値への注目
「見た目」より「中身」を重視する姿勢が明確になっています。「フィラーコンテンツ」の概念導入や、再パッケージされただけのコンテンツへの低評価基準は、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供するウェブサイトを優遇する意図が見えます。 - 誇張表現や専門性の検証強化
「専門家風」の表現や資格の誇張に対する警告は、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の評価をより実質的なものにしようとする試みだと思います。主張だけでなく、実際の内容や検証可能な情報に基づいて評価するというのは理にかなっています。
これらの変更は、SEO業界全体に大きな影響を与えるでしょう。特にAIツールを活用したコンテンツ制作が普及している現在、単なる「効率化」ではなく、どうAIを活用しながら独自性や付加価値を生み出すかが重要になると考えます。
最終的には、この改定はユーザーにとって良い変化だと思います。検索結果から低品質なAI生成コンテンツやスパムが減り、真に価値のある情報へのアクセスが向上するはずです。ただし、コンテンツ制作者にとっては、より高い基準と創造性が求められるようになり、一定の調整期間が必要かもしれません。





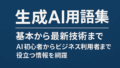


コメント