2024年のクリスマスの約束は2部構成だった。1部は2009年に放送された「22’50”」だった。録画があるので、なんども見ている映像だったけど何度見ても泣ける。
この「22’50”」についていきものがかりの水野良樹がXに投稿していた。視聴している僕にはうかがい知れない苦労や感動がそこに書き込まれていた。ボーカリストが一堂に会して歌うとこんなにすごいものが出来るんだ。何度見ても感動出来というのはそれだけの熱量がこちらに伝わってきているからだと思う。
「クリスマスの約束」最終回。
第1部は2009年「22’50”」の映像。久々にじっくり見た。以前、自分の本にそのときのことを書いたことを思い出して、再読した。8年くらい前に書いた文章。みなさんの記憶の補助線にでもなればいいかなと思って、以下に載せます。(2016年に書いた「いきものがたり」(小学館)という本の抜粋です。わずかに修正してます)
———————————-
第39回 22’50” 2009年の夏頃、小田さんからふたたび、声がかかった。
「クリスマスの約束」で新しい企画を考えている。何組かのアーティストで話し合いの機会をもちたいから、君たちも来てくれないか。2006年に番組に出演して以来、小田さんに会いにいくのは久しぶりだった。
言われた通りに文化村スタジオに3人で出向くと、中心に小田さんを囲んで、何組かの先輩アーティストたちが集まっていた。小田さんが計画していることを話しだすと、僕らだけではなく先輩たちも含め一同、押し黙った。
20組から30組ののぼる大勢のアーティストたちを集めて、それぞれの代表曲をメドレーでつなぎ、しかも全員ユニゾンで声を合わせて客席に届ける。プロのボーカリストたちの声が重なり、ぶつかりあうことで、今まで経験したことのない景色が見える。それを実現したい。小田さんが話し始めたことは、そんな壮大なことだった。
それがどれほどの感動を与えうるものになるのか。そもそもエンターテインメントとして成立するのか。まだその段階では小田さん以外の誰もが想像できていなかった。それぞれ音楽やステージに対する姿勢、考え方がバラバラの数十組のアーティストが、長いリハーサル期間を経て、そんなことを実現できるのか。
メドレーというかたちに対して抵抗感を持つ方もいるはずだ。コラボレーションに対して、お互いが高い意識をもって取り組むことは簡単ではない。理解を得るために充分な説明をしなければならないし、各アーティストにかける負担は大きい。その場では否定的な意見が、いくつも出た。
それから数ヶ月にわたり、幾度となく小田さんの事務所に呼ばれ、ミーティングを重ねていった。
2009年の夏から秋にかけてのことだ。その頃、いきものがかりのスケジュールは、ライブツアーと連続するシングルのリリースで嵐のなかにあった。3人揃って打ち合わせに参加するのは難しいとなって、代表して水野がひとりで出向くことになった。
スターダスト⭐︎レビュー根本要。スキマスイッチ大橋卓弥、常田真太郎、いきものがかり水野良樹、そして御大、小田和正。毎回、深夜にまで及ぶミーティング。この5人のことを、小田さんはいつからか「小委員会」と呼んでいた。後の委員会バンドだ。とにかく、1から10まで、とことん話し合った。
番組で放送された映像のなかでは「小田さんが見えているビジョンが理解できずに、なんでもかんでも反対する他の4人」のような構図に見えていたが、実際はそうでもなかった。5人ともこの企画を少しでもよいかたちで成功させたいという意志を持っていた。5人はむしろ同じ方向を見ていたと思う。
繰り返し企画を練り直す。さんざんに構成を詰めて、各アーティストたちへの打診も終え、結果、小田さんを含め21組34人のアーティストが集まることになった。
それぞれのアーティストの代表曲をつなげて完成させたメドレー。当初の想定だった全員ユニゾンはハーモニーを多用するかたちに変更され、小田さんが書き上げた全曲、全パートの譜面は計13枚。メドレーの総時間は22分50秒。
予想通りの大作となり、そこからは来る日も来る日も続く、長いリハーサルに入った。
リハーサルスタジオではいつも、小田さんと、このロングパフォーマンスの演奏を一手に引き受けるサポートバンドの皆さんたちが僕らを待ち受けていた。
小田さん以外の20組のアーティストはそれぞれ多忙なスケジュールの合間を縫って、時間をみつけてはスタジオを訪れ、互いのパートを確認しあいながら練習を重ねていく。
スタジオを訪れる側の自分たちはまだいい。1週間に1度ほど顔を出して、自分のパートを中心に練習すれば許してもらえる。だが、小田さんをはじめ、サポートバンドの皆さんはその22分50秒の大メドレーを、スタジオを訪れる各アーティストたちのために、1日に何度も演奏し、明けても暮れても同じリハーサルを繰り返さなくてはならない。それが本番までの数十日間にわたって続く。過酷すぎる。
徐々にリハーサルが進み、大まかなイメージも見えてきた頃、21組34人全員が一堂に会することができるのは、本番当日のたった1回だけということが判明した。それぞれに現在進行形で稼働している21組すべてのアーティストのスケジュールを合わせることは、やはり尋常ではないことだった。
いつのまにか世代もジャンルもバラバラの各アーティストのあいだに、チームワークのような感覚が生まれていく。互いに譜面を確認し合い、声を掛け合う。今回の番組で初めて会う方ばかりだった。キャリアで言えば、先輩も後輩もごっちゃに入り混じっている。でも、誰かを萎縮させるような緊張感はない。さながらそこは学校のようで、まるで気心知れた友人たちと言葉を交わしているよう。騒がしくも楽しい空気がスタジオには満ちていた。
「音楽をつくっていると、どうしても個人競技になりがちなんだけれど、俺は一度、集団競技みたいなことをやってみたかったんだ」
みんながわいわいと、ひとつの歌について、ああでもない、こうでもないと会話をしている。そんな光景を目の前にして、いつかのミーティングで小田さんがつぶやいた、そんな言葉を思い出した。
本番の日を、迎えた。
小委員会のメンバーたちで膨大なミーティングを重ねた結果、大メドレーの基本スタイルが決定した。楽曲の主旋律を、その曲を持ち歌とするシンガーが座組の中心で歌う。他の33人はハーモニーで声を重ね、そのひとりの歌声を全員で支える。そのかたちで楽曲ごとに、たすきを繋ぐようにみんなで交代しながら歌い継いでいく。
メドレーのタイトルは、その総時間をそのままとって「22’50”」とされた。
会場は幕張メッセ。
5000人の客席にメドレーのことは知らされていない。当然ながら、これからなにが起こるのか全く知らない観客たち。モニターから客席を覗けば、みんなそわそわとしながら開幕を心待ちにしている。冒頭、小田さんや要さん、スキマスイッチの大橋さんに吉岡も加わって、オープニングアクト的に「クリスマス・イブ」や「きよしこの夜」などの数曲が披露された。
これまでの小委員会の打ち合わせの模様やリハーサルの光景などを収めた短いドキュメンタリーが会場に流される。そのあいだに僕ら出演者たちは、全員が舞台袖にスタンバイした。それは大事な試合に臨む、チームそのものの姿だった。34人、顔が上気していた。
暗転となり、立ち位置につく。まだ客席はこれから何が起ころうとしているのか気づいていない。いや、ステージに上がった僕らも、本当の意味では気づけていなかったのかもしれない。これからどんな奇跡が起こるのか。どんな光景が目の前に広がるのか。
照明がついた。
観客の声は、驚きと湧き上がる期待で、低く揺れた。観客の声に、今度はステージ上の僕らを包む空気が一変する。あのときの空気の変化を、僕はおそらく一生忘れないだろう。
リハーサルでは笑顔で声をかけあっていたアーティストたちの顔が、みんな一瞬にして”本番”の表情へと変わった。さっきまで”友人”であったはずのひとたちが、舞台において、眩しい魅力を解き放つ。彼らはシンガーに変貌した。輝きは、突然放たれた。
オープニング曲。このメドレーのテーマとも言える「この日のこと」を34人全員で歌い終えると、ついにソロパートへと入る。
すでに興奮している観客席のなかで、めいいっぱいに膨らんでしまった期待感のかたまりが、ステージに押し寄せてくるのがわかる。この空気をいったい誰が受け止められるというのだ。そう思った直後、ひとりの男性が前に歩み出した。
なにひとつ慌てることはない。自分がそこに立つことは当然であると言うように堂々と、そしてゆっくりと、そのひとは歩き出した。メインマイクの前に立ち、観客全ての視線を悠然と受け止めて、彼は大きく手を広げた。その背中では、聴き慣れたイントロが鳴り出している。藤井フミヤさんだった。
「振り返ると いつも君が 笑ってくれた」
名曲「TRUE LOVE」のあまりにも有名な一節。
これがシンガーか。これがスターか。同じステージに立ってみて、その背中を目の前で見て、初めて感じる凄みがそこにはあった。だが、シンガーとしての唯一無二の輝きをみせつけてくれたのは、もちろんフミヤさんだけではなかった。そこから次々と歌が、舞台の上に立ち続けてきた一流のシンガーたちによって、歌い継がれていく。どなたもリハーサルとは比べものにならないくらいの声量、存在感。
いつか誰かに言われた言葉を思い出した。
「プロとアマチュアの違いをあえて言うのなら、アマチュアはリハーサルで最高まで磨いて本番はそのちょっと下をいくんだ。だけどもプロは、客前に立ったときにちゃんと化けて、本番で最高のちょっと上をいく」
大勢の観衆の視線を一身に受けたときに、シンガーたちが自分の肉体にみなぎらせるパワーは本当に凄まじかった。その眩しい背中が21組も続く。彼らが見ている景色をともにし、彼らと想いをひとつにしながら、自分もそのステージに立っている。
こんな経験は、もう絶対に味わえない。奇跡のなかにいた。
22曲目。ついにたどりついた最後の楽曲。
ひとりの女性シンガーが前へと歩み出した。
いきものがかりのボーカルだった。吉岡聖恵だ。「帰りたくなったよ」
小田さんがラストにこの曲を選んだ理由は、今もまだ聞いていない。吉岡は22曲にわたってつながれたバトンを、大事に丁寧に、そして堂々とゴールへと運び、最後の一節まで歌い切った。
拍手は10分ほど、鳴り止まなかった。
その途絶えることのない拍手のなかで舞台上の34人が、それぞれに手をつかみ合い、抱き合い、涙をこぼした。
誰もがこの興奮を言葉にしようと必死になっていたけれど、それはもう会話にならない。ただ「すごい!すごい!」「なんだこれ」「わぁぁぁ」と、感嘆の声だけが舞台上に、何度も生まれては消えるばかりだった。
小田さんがマイクを持って言う。
「おそらくこれは、僕が人生で聞いた、一番長い拍手だったでしょう」
あのとき、自分はまだ27歳になる少し、手前だった。あの舞台の上で過ごした22分50秒の時間。そのとき感じた興奮、眺めた光景、触れてしまった奇跡。
それらはすべてこれから先、この世界を歩むうえで、大きな”基準”となる。
自分はおそらく、これからしばらく、この光景を目指し、日々を過ごしていくのだろう。そう思った。
————————–
「いきものがたり」水野良樹(小学館:2016年刊行)
(※文章は一部、編集しています)



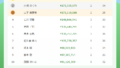
コメント