
投資信託の最新情報:2025年の人気・純資産額・資金増減動向
投資信託市場は2025年に入っても、引き続き日本の個人投資家から高い関心を集めています。新NISAの効果や米国株式市場への期待感を背景に、多くの投資信託が資金流入を記録しています。今回は2025年の3月までの最新の投資信託市場の動向を純資産額や人気ファンド、資金増減の観点から詳しく解説していきます。
投資信託市場の現状:純資産総額と資金流入動向
2025年に入ってからの投資信託市場は、全体として堅調な資金流入傾向が続いています。1月には月間資金流入額が過去最高の2兆1,212億円を記録し、初めて月間で2兆円の大台を突破。これは2007年3月に記録した過去最高額(1兆8,886億円)を約18年ぶりに更新する快挙でした。
2月も1兆6,066億円の資金流入となり、高水準を維持。しかし、2月は運用による評価減が6兆2,781億円と大幅なマイナスとなったため、純資産総額は前月比4兆9,189億円減の137兆4,959億円となりました。この結果、4カ月連続で更新していた純資産総額の最高額記録更新が止まることになりました。
3月の資金流入額は1兆5,862億円と引き続き高水準を維持し、資金流入超過は22カ月連続、1兆円超えは3カ月連続となっています。
この背景には、新NISAの普及と米国株式市場への関心の高まりがあります。特に年初の新NISA枠の利用可能開始時には一括投資による資金流入が多く見られましたが、その後はペースが落ち着きつつも堅調な流入が続いています。
人気ファンドの最新ランキング:純資産額トップは?
2025年4月現在の純資産残高ランキングによると、トップの座を守っているのは「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」で、純資産額は約5兆9,872億円に達しています。2位は「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」の約5兆1,006億円、3位は「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース(為替ヘッジなし) 予想分配金提示型」の約2兆8,145億円と続いています。
上位10ファンドを見ると、米国株式型や全世界株式型が多くを占めており、特に米国株への投資比率が高いファンドが上位にランクインしています。これは、低コストのインデックスファンドへの人気と、米国株式市場への期待感が高まっていることを反映しています。
投資資金の流入先:米国株式への集中が顕著に
2025年の資金流入の特徴として、米国株式型ファンドへの集中傾向が顕著になっています。2025年1月の資金流入額上位10ファンドを見ると、米国株式型が6ファンド、グローバル株式型が4ファンドとなっていますが、グローバル株式型ファンドも米国株の比率が高いものが多く、「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」では米国株比率が66.1%(1月末時点)、「インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)」では51.2%(12月末時点)となっています。
2月の投資信託市場は米国株の下落による影響を大きく受け、純資産総額上位10ファンドの月間収益率は軒並みマイナスとなりました。特に米国株式ファンドの下落が目立ち、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース」は9.06%の下落、「ネットウィン GSテクノロジー株式ファンドBコース」は9.18%の下落となりました。
3月の資金流入ランキングでは、「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」(通称オルカン)が推計1,864億円で首位となり、前月1位だった「米国株式(S&P500)」は1,775億円で2位となりました。また、注目すべき点として「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)」が推計241億円の資金流入を記録し、設定以来初めてトップ10入りを果たしました。
2007年から2025年:投資信託市場の変化
2007年と2025年の投資信託市場を比較すると、投資家の選好に大きな変化が見られます。2007年当時の資金流入額上位10ファンドは毎月分配型ファンドを中心に分配金重視のファンドが目立ち、上位10ファンドのうち半数が毎月分配型ファンドでした。投資対象も株式、債券、REIT、バランスファンドと多岐にわたっていました。
一方、2025年現在では、分配金重視のファンドへの偏りは解消され、毎月分配型は上位10ファンド中3ファンドに減少。分配頻度も年1回が5ファンド、年2回が2ファンドと増加しています。しかし、投資対象は米国株式に大きく偏っており、特定市場への集中リスクが高まっていると言えます。
新NISA時代の投資信託新設動向
2025年2月の新規設定ファンドは24本で、設定額は約1,080億円となりました。新規設定ファンドの中で最も注目を集めたのは「野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド」(野村)で、設定額は約850億円に達しました。このファンドは国内籍公募投信で初めて非上場インフラ企業の株式を主要投資対象とするもので、先進国の非上場インフラ企業の株式に投資する新しいタイプの投資信託です。
2位は「HSBCグローバル・ターゲット利回り債券F2025-02」(HSBC)で、設定額は約100億円。このファンドは信託期間約5年の間に満期を迎える世界各国の企業等が発行する債券を主要投資対象とし、対円で為替ヘッジを行い満期まで持ち切ることで、円ベースで安定したリターンの獲得を目標としています。
長期人気ファンドの現状:ひふみプラスの苦戦
かつて日本を代表するアクティブファンドとして人気を博した「ひふみプラス」は、近年苦戦が続いています。「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025」では「もっとがんばりま賞」として紹介されるなど、成績改善が期待される状況にあります。
純資産額は3,000億円以上と保有者は多いものの、過去5年、3年、1年の成績はいずれもTOPIXを大幅に下回り、最大下落率も平均より大きく、下がりにくさや成績の安定度も低得点となっています。
設定当初は中小型の成長株に投資し好成績で人気を集めましたが、純資産額の急増により運用戦略の変更を余儀なくされ、大型株メインの運用に切り替え、さらに海外株も一部組み入れるなどの対応を行いました。しかし、成績は依然として日本株総合部門の下位を脱却できていません。
2025年1月には運用会社のレオス・キャピタルワークスが体制変更を発表し、藤野英人氏は「ひふみ投信」シリーズなどの運用に専念するとしており、今後の復活に期待が集まっています。運用当初(2012年5月)に28.4%だった成長企業への投資比率は、2025年2月には2.65%と大幅に減少しており、投資戦略の変化が顕著です。
今後の投資信託市場の見通し
2025年に入り投資信託市場は引き続き活況を呈していますが、特定の資産クラス(特に米国株式)への集中リスクが高まっています。米国株式市場が2月に調整したように、今後も市場変動のリスクは常に存在します。
一方で、ゴールド関連のファンドが注目を集め始めるなど、投資家の関心の多様化も見られ始めています。3月に「ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)」が初めて資金流入トップ10入りしたことは、投資家がポートフォリオの分散を意識し始めている可能性を示唆しています。
日本の投資信託市場は新NISAの導入により、今後も個人投資家からの資金流入が期待されます。その中で、低コストのインデックスファンドへの人気は継続すると見られる一方、市場環境の変化に応じて、投資対象の多様化が進む可能性もあります。特に、資源・エネルギー、インフラ、不動産など、インフレヘッジとなり得る資産への投資機会が注目される可能性があります。
まとめ:投資信託選びのポイント
2025年の投資信託市場を見ると、資金流入は堅調に続く一方で、米国株式への集中という新たなリスクも顕在化しています。投資家としては以下のポイントに注意することが重要でしょう。
- 資産クラスの分散:米国株式への集中が高まっている現状では、意識的に他の資産クラスも組み合わせることで、リスク分散を図ることが重要です。
- コスト意識:「eMAXIS Slim」シリーズのような低コストのインデックスファンドが人気を集めていますが、自分の投資スタイルに合ったファンドを選ぶことが大切です。
- 長期視点:資金流入額が多いファンドが必ずしも今後も好成績を残すとは限りません。短期的な人気に惑わされず、長期的な運用実績や投資哲学を重視しましょう。
- 定期的な見直し:「ひふみプラス」の例のように、かつて人気を博したファンドでも成績が低迷するケースもあります。定期的に保有ファンドの成績を確認し、必要に応じて見直すことも検討しましょう。
投資信託市場は常に変化し続けています。最新の情報を収集しながら、自分自身の投資目標やリスク許容度に合った投資判断を心がけることが、長期的な資産形成の鍵となるでしょう。
私はeMAXIS Slim米国株式(S&P500)をNISAの積み立て投資と成長投資枠で購入しています。月々の積み立てと下がったときに成長投資枠で買うという戦略です。現在はS&P500が下がっているので損益はマイナスですが、安くなっているので成長投資枠はちょこちょこ買っています。
また、PAYPAYのポイント運用はS&P500からゴールドに変えて買っているのでこちらは含み益です。

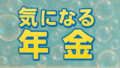
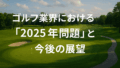
コメント