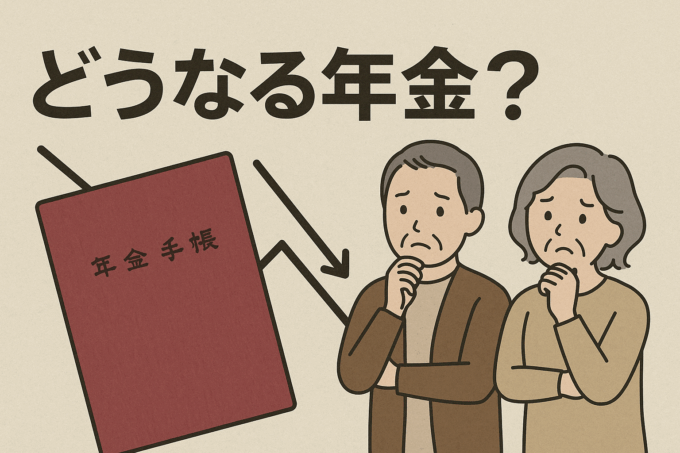
年金、どうなるの? 退職間近な私が日経記事を読んで考えたこと
皆さん、こんにちは。いよいよ私もあと数年で、いわゆる「年金生活」に突入する年齢になりました。長年働き、毎月給料から年金保険料が引かれていくのを見て、「この積み重ねが、老後の支えになるんだな」と漠然と考えてきました。
ところが先日、日本経済新聞の記事を読んで、正直なところ、不安が募ってしまいました。記事の見出しには「低年金対策、相次ぎ後退」「基礎年金底上げを削除」「自民内で法案提出に異論」と、私たちの老後生活に直結する、穏やかでない言葉が並んでいました。
これから年金を受け取る立場になる私にとって、このニュースは他人事ではありません。一体、私たちの年金はどうなってしまうのか。記事の内容を、私のような「これから年金生活者」の視点から読み解き、考えてみたいと思います。
消えてしまった「基礎年金底上げ策」
記事によると、政府は今国会で年金制度の改革法案を出そうとしていたそうですね。その中核の一つが、低年金対策、特に「基礎年金(国民年金)の底上げ」だったといいます。基礎年金というのは、日本に住んでいる20歳から60歳までの全ての人が加入する、年金制度の「1階部分」です。自営業の方も、会社員の方も、専業主婦(夫)の方も、みんながこの基礎年金を受け取ることになります。
記事には、この基礎年金が、将来的に3割も目減りする可能性があると書かれていました。3割ですよ! 今でさえ、満額でも月に約6万9千円(2025年度予想)と、これだけで暮らしていくには心もとない金額なのに、さらにそこから3割も減ってしまうなんて、想像しただけでゾッとします。
厚生労働省は、この将来的な目減りを少しでも食い止めるために、厚生年金から一部財源を移したり、国庫負担を増やしたりして、将来の基礎年金を「何もしない場合より3割底上げする」という改革を検討していたそうです。つまり、将来もらえるはずの年金が大幅に減るのを、少しでも改善しようとしていたわけです。
しかし、この記事によると、この大事な「基礎年金底上げ策」が、今回の改革法案から削除されてしまったというのです。理由は、自民党内で反対論が強かったから。特に、厚生年金が先に減額されることや、国庫負担の財源をどうするかといった点が問題視されたようです。加えて、夏の参議院選挙への影響を懸念する声も大きかったとのこと。
私たちの将来の安心のための対策が、政治的な理由で見送られてしまうなんて、非常に残念ですし、正直なところ腹立たしい気持ちになります。
後退する低年金対策、私たちの不安は募るばかり
今回の基礎年金底上げ策の削除だけでなく、記事には他の低年金対策も相次いで後退していると書かれています。
一つは、基礎年金保険料の納付期間を今の40年から5年延ばして45年にするという案です。これは、年金を受け取る期間は延びるのに、保険料を払う期間は変わらないという現状を踏まえ、給付と負担のバランスをとるという側面もあったのでしょう。納付期間が5年延びれば、年間の年金額は約10万円増える見込みだったそうです。しかし、これには保険料の負担が合計で100万円増えることになり、国民の強い反発を受けて早々に断念されたとのこと。年金が増えるのはありがたいですが、退職が近づく世代にとって、今さら100万円もの追加負担は厳しいという声が多かったのでしょう、気持ちは分かります。でも、将来の給付のために何か手を打たないといけない、というのもまた事実です。
もう一つは、パートやアルバイトで働く方の厚生年金への加入を拡大する動きです。厚生年金に加入できれば、基礎年金に上乗せして年金を受け取れるようになりますし、基礎年金全体の財政改善にも繋がります。これは低年金になりがちな非正規雇用の方々にとって、非常に重要な対策です。しかし、これも保険料の半分を負担する事業主への配慮を求める声が自民党内で強く、拡大完了の時期が2029年から2035年まで、なんと6年も先送りされたそうです。
こうした、低年金になるリスクを抱えている人たちを救うための対策が、次々と頓挫したり、先延ばしになったりしている状況を見て、これから年金生活に入る私たちは、ますます不安を感じざるを得ません。
記事にもありましたが、今の基礎年金満額月6.9万円でも厳しいのに、今後さらに水準が下がれば、生活に困窮する人が増え、生活保護に頼らざるを得なくなるリスクが高まります。低年金対策が遅れれば遅れるほど、この問題は深刻になっていく一方です。
選挙優先?政治の「逃げの姿勢」に疑問
なぜ、私たちの将来の安心のために必要な改革が、このように後退してしまうのでしょうか。記事を読むと、その背景には「選挙」があることが透けて見えます。年金改革は、誰かの負担が増えたり、給付が減ったりと、「ゼロサムゲーム」の側面があるため、国民に痛みを伴う説明をし、理解を得る必要があります。しかし、政府・与党は、夏の参議院選挙を前に、国民が反発しそうな改革に正面から向き合う姿勢を欠き、法案提出そのものを見送るべきだ、という意見まで出ているというのです。
かつて、旧社会保険庁の年金記録問題、いわゆる「消えた年金」問題で自民党が大敗し、政権交代に繋がった苦い経験があります。年金は自民党にとって「鬼門」なのだと記事は指摘しています。だからこそ、選挙を恐れて改革から逃げてしまう。
しかし、別の記事には、この政治の「逃げの姿勢」こそが、少子高齢化に克てない最大の要因であり、将来世代、特に就職氷河期世代にツケを回しているのだという厳しい指摘がありました。就職氷河期世代は、非正規雇用に長く置かれた人が多く、報酬比例の厚生年金が薄いため、基礎年金への依存度が高い傾向にあります。その基礎年金が将来的に大幅に下がれば、彼らの生活はより一層苦しくなる。生活保護との逆転現象が強まり、保護申請が急増する事態も起こりうるというのです。
今の引退世代が、2004年の制度改正で想定していた以上に多くの年金を受け取っていることが、将来世代の基礎年金が目減りする根本原因の一つだと記事は書いています。本来なら、この現状を国民に説明し、理解を求めて是正するのが政治の責任のはずです。しかし、政府・与党にはそれができる覚悟と自信がなく、選挙を前に白旗を揚げてしまった。
「年金を政争の具にするな」という言葉は、これまで政権が年金改正案を出すたびに訴えてきた言葉です。それなのに、自らが政争を恐れて改革から逃げている。これでは、年金の未来が本当に心配になります。
じゃあ、私たちはどうすればいいの?
政治の動きに不安を感じてばかりいても仕方ありません。私たち自身で、来るべき年金生活に向けて、できる限りの備えを進めることが、これまで以上に重要になった、と記事を読んで強く感じました。
記事にも書かれていた、私たち自身でできる対策を改めて考えてみましょう。
長く働くこと: これが一番分かりやすい対策かもしれません。給与収入を得られる期間が延びるだけでなく、会社員や公務員として厚生年金保険料を納め続ければ、将来もらえる厚生年金額を増やすことができます。記事には、69歳まで厚生年金保険料を納めることで月々の年金額を増やせるとあります。もちろん、健康状態や仕事の状況にもよりますが、可能な範囲で長く働くことを検討する価値は大きいでしょう。
年金の受け取り開始を遅らせる(繰り下げ受給): 公的年金は、原則65歳から受け取りが始まりますが、希望すれば66歳以降に遅らせることができます。1年遅らせるごとに、月々の年金額が8.4%増える仕組みです。例えば、70歳まで繰り下げれば、65歳から受け取る場合の1.42倍(8.4% × 5年 = 42%増)の年金額を一生涯受け取ることができます。これは非常に強力な年金額アップの方法です。65歳から年金を受け取らなくても、当面の生活費を給与や貯蓄で賄えるのであれば、「長生きリスク」、つまり予想以上に長生きして資金が枯渇するリスクへの耐性を高めることができます。ただし、いつまで生きるかは誰にも分からないため、繰り下げ中に万が一のことがあった場合のことも考えておく必要があります。
資産運用を活用する(NISAやiDeCoなど): 公的年金だけで十分な老後資金を確保するのが難しい現状では、自助努力で資産を増やすことも真剣に考える必要があります。少額投資非課税制度(NISA)や個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)といった税制優遇のある制度を活用して、計画的に資産形成に取り組むことが有効です。もちろん投資にはリスクが伴いますが、長期・積立・分散といった基本的な考え方を理解し、自分に合った方法で少しずつでも始めることが大切です。
まとめ:不安はあっても、自分でできることはある
今回の年金改革の後退に関するニュースは、私たちこれから年金生活を迎える世代にとって、非常に厳しい現実を突きつけるものでした。将来の基礎年金が目減りするリスク、低年金対策が進まない現状、そして選挙を優先して改革から逃げる政治の姿勢。どれも不安を煽るものばかりです。
しかし、政治の動向を見守りつつも、私たち自身でできる準備があることも、記事は教えてくれました。長く働くこと、年金の受け取り開始を遅らせること、そしてNISAやiDeCoなどを活用して資産を増やすこと。これらは全て、自分自身の力で、将来の不安を少しでも和らげるための具体的な行動です。
もちろん、こうした自助努力だけで全てを賄えるわけではありません。やはり、公的年金制度が将来にわたって持続可能であり、特に低年金の方々が安心して暮らせるような、安定した制度であってほしいと強く願います。そのためにも、私たちは政治の動向を注視し、必要な改革をしっかりと進めてほしいと声を上げていく必要があるのかもしれません。
まずは、自分自身の年金見込み額を確認し、将来の生活設計を具体的に立ててみること。そして、今回ご紹介したような自助努力の選択肢について、真剣に考えてみることから始めてみてはいかがでしょうか。私も、今回の記事をきっかけに、改めて自身の老後資金について深く考え直し、できる限りの備えを進めていこうと決意しました。一緒に、来るべき年金生活に向けて、今できることを始めていきましょう。
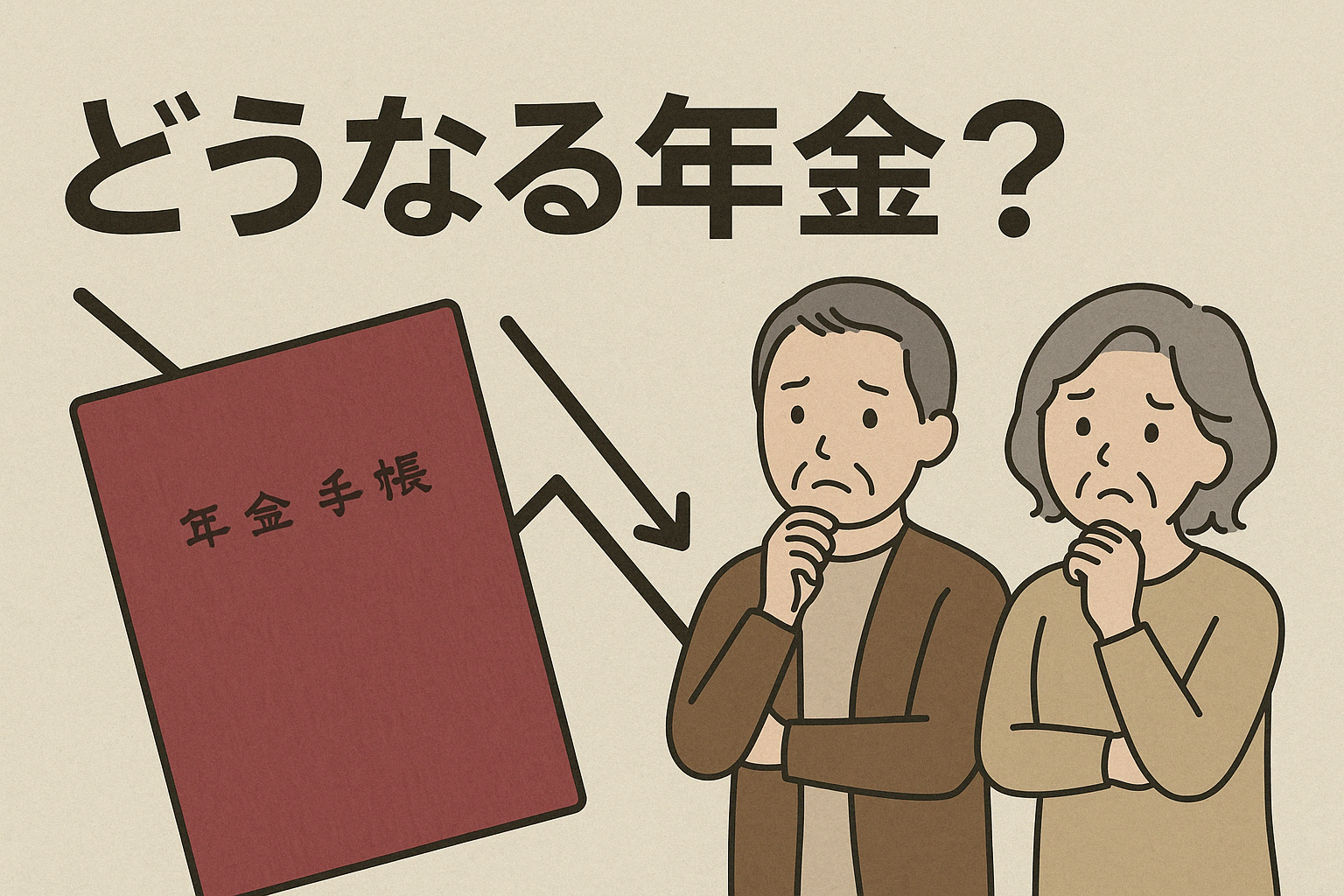

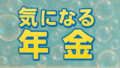
コメント