今朝の日経に『株価急落時、売却は逆効果も。積み立て投資、継続が重要』という記事がありました。これについて私なりに考えてみました。
株価が下落するとき、どう向き合うか
―― 投資初心者の動揺と、落ち着いて乗り切るための視点
2025年春、日米の株式市場に大きな変動がありました。
特に影響が大きかったのが、2024年から始まった新NISA制度をきっかけに投資を始めた人たち。多くが初めて「大きな下落」を経験する局面となりました。
この急落を前に、どう感じ、どのように対応すべきか。
短期的な感情ではなく、中長期の視点から整理することが重要です。
「初めての下落」への動揺
ここ数年、株式市場は比較的順調な推移を見せていました。
2020年のコロナショック後、各国の金融緩和を背景に株価は大きく回復し、その後も高水準を維持してきました。
そんななか、2025年4月にかけて、トランプ前大統領の関税政策再開への警戒感や中東情勢の不安定化を背景に、市場は不安定な展開となりました。
新NISAの制度設計により、2024年には約1,400万人が新たに口座を開設。うち多くが初心者であり、今回のような「大きく下がる相場」は初めての体験になります。
SNSや証券アプリの「真っ赤な数字」に戸惑った方も多いはずです。
売却という選択が招く“落とし穴”
このような局面では、評価損が拡大することで「元本がなくなるのでは」と不安にかられ、資産を売却する行動をとる人もいます。
しかし、これは長期投資において逆効果となることが多い、というデータがあります。
米資産運用大手・キャピタルグループの試算によると、
2004年末に世界株式インデックスへ100万円を投資し、何もせずに20年間運用を続けた場合、資産は743万円に増加(年率10.5%)しました。
ところが、その間の「上昇率が高かった上位10日」を逃すと、資産額は349万円と半減します。
20日逃すと219万円にまで減少。
言い換えると、「大きく上がる数日は、暴落局面に集中している」ことがわかります。
実際、リーマンショック期(2008年秋)や、コロナショック期(2020年3月)に上位の上昇日が集中していました。
つまり、相場が不安定なときこそ、大きく上がるチャンスも同時に存在するということです。
継続する投資の強さ
積立投資を行っている場合、価格が下がったときに多くの口数を買えるという特徴があります。
これを「ドルコスト平均法」と呼びます。
仮に毎月1万円を積み立てるとして、
株価が高い時には少量を、株価が下がった時には多く買う。
この繰り返しにより、取得単価が平均化され、長期的にはリターンの安定性が高まると言われます。
今回のような局面は、長期視点でみれば「安く仕込めるチャンス」にもなります。
実際、多くのインデックスファンドでは、暴落時の積立が後年の利益を支える“起点”になるケースが目立ちます。
「余裕資金」で投資しているか
ファイナンシャル・プランナーの横田健一氏は、
「運用を続けるには、まず余裕資金で行うことが最も重要」と語ります。
資金は以下のように4つに分類して考えるのが有効です。
- 生活費(毎月必要な支出)
- 緊急予備資金(病気・災害などへの備え)
- 近い将来に使う資金(教育・住宅・介護など)
- 余裕資金(5年以上使う予定がない資金)
この「余裕資金」の範囲内で投資を行っていれば、短期的な下落にも冷静に対応できます。
特に退職後の人にとっては、「取り崩すタイミングをずらす」という選択肢がとれるかどうかが重要です。手元に現預金があれば、下落時にはそちらから支出し、相場回復を待つことができるためです。
個別株への対応は慎重に
一方、個別株に投資している人は、ナンピン買いを考える場面があるかもしれません。
たとえば、500円で1000株買った銘柄が400円に下がった際、もう1000株買い増せば、平均取得単価は450円になります。
株価が450円に戻れば、収支は±0に。
ただし、問題はその企業の「下がっている理由」が相場全体の影響なのか、企業固有の業績悪化なのかを見極めることです。
松井証券の窪田朋一郎アナリストは、
「根拠なきナンピン買いはリスクが高い。銘柄の将来性や成長性の根拠を持てるかどうかがカギ」と指摘しています。
ベア型ファンドは初心者向きではない
相場下落時に価格が上がる「ベア型ファンド」も注目されやすい商品です。
一見便利に見えますが、長期保有に向かないというデメリットがあります。
ベア型ファンドは、対象指数が下がることで価格が上がる構造ですが、日々の値動きに連動する仕組みであるため、相場が上下を繰り返すと資産価値は徐々に減価します。
東海東京インテリジェンス・ラボの仙石誠氏は、
「初心者には推奨できず、短期のヘッジ目的に限るのが無難」とコメントしています。
投資の原則を、改めて確認する
株式市場の変動は避けられません。
しかし、その変動のなかでも「売らずに保有し続ける」ことが、長期投資の最大の強みとなる――これは多くのデータが示しています。
- 焦って売らない
- 生活に必要な資金は投資に使わない
- 積立を止めず、淡々と継続する
- 企業や商品の「中身」を見て投資判断を下す
こうした基本を忘れずに、冷静に行動することが、
今回のような局面を乗り越えるための最善策といえるでしょう。
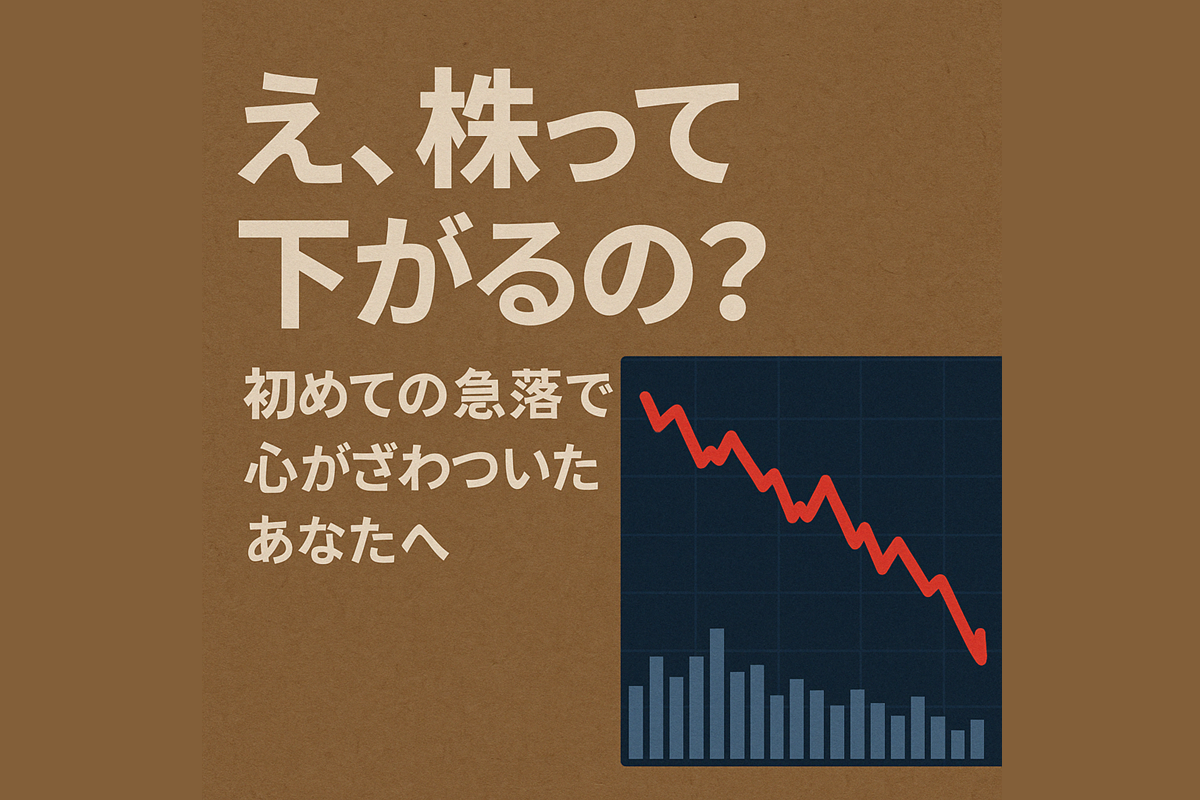




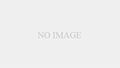

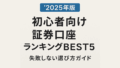
コメント